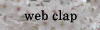渚のInvitation3
翌朝。
シュラは隣のベッドで寝ている紫龍が動く気配で目を覚ました。
聖闘士の習性なのか、そばで誰かが動くとすぐに目が覚めてしまうのだ。
「起きたのか、紫龍?」
「あ、はい。すみません、起こしてしまいましたか?」
声をかけると、申し訳なさそうな声が返ってきた。時計を見ると、まだ6時前だった。
「習性だからな。お前もそうだろう?」
聖闘士は人の気配に敏感だ。いつどこで、どんな敵が襲いかかってくるかわからない。それは寝ている時も同じで、常に感覚の一部が研ぎ澄まされている。
「ええ、そうですけど。でも、すみません、起こしてしまって」
「いきなりは無理かもしれないが、俺にそこまで気を遣わなくてもいいぞ。せっかく二人で旅行に来てるんだからな」
老師の教育の賜物なのか、紫龍は年上に対する礼儀を欠かさない。ましてや、シュラは一度闘った縁で何かと接点が多いとはいえ、共に過ごした時間は決して長いとは言えない。紫龍が恐縮するのも無理はなかった。
「で、こんなに早く起きてどうするんだ?」
「外を走ってこようと思うんです」
「走るって……」
このホテルの敷地はかなりの広さがある。その周囲を走るにしても、普通の人間ならばちょうどいいランニングコースなんだろうが、聖闘士であるシュラたちにとっては短すぎる距離だ。しかも、彼らのスピードをもってすれば、このホテルの周囲を走るのに要する時間は、ほんの数秒で済んでしまう。
「いつもこの時間には起きて、家の周りを走るんです」
言いながらベッドを下りる紫龍に、シュラは思っていることをそのまま伝えた。すると、そんなに速く走るわけではないから、という返事が返ってきた。
「シュラも一緒にどうですか?」
「……そうだな。俺も、旅行に出ている間に身体が鈍ってしまっては、アテナに申し訳が立たない。付き合おう」
もともと、シュラは睡眠時間が長い方ではない。いつも起き出す時間はもう少し遅いが、それでも睡眠時間はいつも以上に取っている。昨夜も、紫龍が床に入ってからあまり時間を置かずにシュラも横になったのだ。
シュラはTシャツにGパンというラフな格好に着替えた。紫龍は……と見ると、いつもどおりの中国服に身を包んでいる。走ると言っていたためか、袖のないタイプの上着だった。
「お前、その格好で行くつもりか?」
「はい。……いけませんか?」
「アテナの家の周囲や聖域ならばそれでもいいが、ここではどうかと思うぞ。他に何か持ってきていないのか?」
「そうですね……」
考える仕草をする紫龍に、シュラは持ってきた服を見せてもらった。そして適当に見繕ってTシャツとコットンパンツに着替えさせた。
「着慣れている服が楽なのはわかるが、旅行に出ている時は一般人のように振舞え、というのがアテナからの絶対命令だからな。ここにいる間は、我慢してくれ」
「はい」
最初の1周は二人並んでゆっくりと走った。だが、普段の10倍もの時間をかけて走るよりは歩いた方がましだ、とすぐに気付いて二人は歩くことに決めた。
朝のさわやかな海風を受けながら、プライベートビーチになっている砂浜へと向かう。
「でも、こういう服はほとんど着たことがなくて……何をどう合わせたらいいのか、わからないんです」
修行地では老師に倣って常にマオカラーの訓練着で過ごしており、城戸邸でもそれで通しているのだという紫龍は、普通にTシャツを着たりGパンをはいたりすることも稀なのだと話した。
「ここに来る前にショップに連れて行かれた、と言ってたな。全部新調してきたんだろう?」
「ええ。色合いはある程度選ばせてもらったんですけど」
「そうか。ここにいる間に、コーディネートも教えてやる。とりあえず、毎日の服は俺が選んでやるから心配するな」
「何から何まで、本当にすみません。ありがとうございます」
紫龍は律儀に頭を下げた。
「気にするな。俺も、そういうのは嫌いじゃないんでな」
特にそれが、一目惚れした想い人であれば尚更である。
「それよりほら、見てみろ。珊瑚の欠片がいっぱい落ちてる」
「あ、本当だ」
二人はプライベートビーチの砂浜へと足を踏み入れた。砂浜には、一面に珊瑚の欠片が打ち上げられている。
「初めて見ました。こんなにたくさん……」
「すでに死んでしまった珊瑚だがな」
「それでも、こんなに綺麗なんですね」
さっきは走っていて気付かなかった珊瑚を見て、紫龍はその傍らにしゃがみこんだ。
「拾っていくか?」
「いいんでしょうか」
「構わないだろう。これも、旅の思い出の一つになる」
「そうですね」
シュラも隣にしゃがみこんで、砂浜に打ち上げられて白く変色した珊瑚に手を伸ばした。一つ、二つとその欠片を拾い上げていく。
「皆さんの分を拾うんですか?」
「ん? そうしてもいいが、老師の分はお前が拾うんだろう?」
問われて、シュラは逆に問い返した。
「そうですね。あと、瞬と星矢と、氷河と一輝の分も拾わないと……」
言いながら、紫龍もシュラに倣って一つ、二つ、三つと珊瑚を見繕っては拾っていく。たちまち、掌には5つの珊瑚が乗っていた。
「全員分となると、あと11個拾わないといけないな、俺は」
「手伝いましょうか?」
「ああ、頼む」
素直に問うてくる紫龍に、シュラは思わず微笑がこぼれた。
二人並んで、無心になって珊瑚を拾う。そんなささやかな時間が、シュラには愛おしく思えた。
紫龍と二人で20個以上の珊瑚を拾い上げて。
シュラは最後に、もう2個珊瑚を拾った。
「それは?」
「俺とお前の分だ。せっかくだから、俺たちも持って帰ろう」
問いかけてくる紫龍に見せた、二人分の珊瑚。
それは「ト」の字形をした、真っ白な、ほとんど同じ大きさの珊瑚だった。
その日は、1日ホテルでゆっくりしよう、と二人で決めていた。
海に向ってせり出しているカフェレストランのテラス席で昼食を取ってから、シュラは部屋のテラスにあるデッキチェアに寝転んだ。生まれ育ったスペインの習慣である昼寝――シエスタである。
「お前も来いよ、気持ちいいぞ」
紫龍が日に焼けないように、と白い大きなパラソルを広げて紫龍はその陰に寝かせる。
「心地よい海風に吹かれながらのシエスタとは、聖闘士にあるまじき贅沢だな」
昼食の後、こうして少しの間短い睡眠を取ることで、午後の集中力や効率を上げる。
シュラは聖域でもこうしてシエスタを欠かさない。紫龍が他の仲間たちと共に女神である沙織を奉じて聖域に攻め込んできた時でさえも、そうだった。
下の宮では激戦が続いており、聖闘士になってからずっと仲間としてつるんでいたデスマスクの小宇宙が消えたのもわかっていた。だが、シュラは敢えていつもと同じように過ごし、平常心を保って紫龍を迎え撃ったのだ。
「だが、こんな贅沢を味わえるのも、お前たちがハーデスを倒して平和をもたらしてくれたおかげだ。お前に感謝しなければな」
「そんな……俺がエリシオンでも闘えたのは、あなたの守りと導きがあったおかげです。感謝しなければならないのは、俺の方だ」
こんな真昼間に転寝をするという習慣のない紫龍は、少し戸惑いながらもシュラに倣って横になっている。
「では、お互い相手に感謝しながらこのシエスタを満喫するとしよう」
礼儀正しくて謙虚なのは紫龍の美徳だが、度を越してしまうとせっかくの楽しみが楽しい時間ではなくなってしまう。
シュラは適当なところで妥協点を提供して、瞼を閉じた。
横になってからすぐに規則正しい寝息を立て始めたシュラを、紫龍はじっと眺めていた。
パラソルで陰になっているデッキチェアに寝転んだものの、いつも夜明けと共に目覚めて夜も8時か9時は寝るという習慣が身についている紫龍は、こんな昼間に転寝をすることはない。
だが、寝返り程度なら大丈夫だが、あまり動くとせっかく寝入ったシュラを起こしてしまう。それだけは避けなければ……と紫龍は思った。
心地よい海風に吹かれながら横になったが、目が冴えていて眠りが訪れる気配はない。
紫龍は寝返りを打って、シュラの方に身体を向けた。
(不思議だな)
目を閉じて眠るシュラの顔を眺めて、紫龍は改めて思った。
星矢たちと共に12宮に攻め込んだ時に出会って、拳を交えて。まさに命がけで倒したはずの彼に、命を救われただけでなく、彼の魂とも言える必殺技まで授けられた。
それからというもの、何度彼の言葉に励まされ、彼が授けてくれた技に助けられたかわからない。
けれど思えば、こうして面と向って共に過ごす時間はほとんどなかった。
冥界から戻ってしばらくの間は、療養も兼ねて聖域に滞在していたが、その時は師匠である天秤座ライブラの童虎が守護する天秤宮に留まっていて、シュラのいる磨羯宮には挨拶程度にしか顔を出せなかったのだ。
いつか、ちゃんとお礼を言わなければ。
もう少し、話をする機会があれば。
そう思っていたものの、何をするでもなく時間を過ごしていた自分が、こうして今シュラの隣に寝転がっている。
こうして、シュラの顔をまじまじと眺めるのも、初めてだった。
いつもは鋭い眼光を放っている目が閉じられて、穏やかな表情に見える。
クセの強い短い黒髪。
鼻が高く、彫りの深い精悍な顔立ち。
聖闘士なのだから当然なのだが、鍛え上げられた肉体。
ボタンを外して肌蹴た胸元から覗く、しっかりとした筋肉に覆われた厚い胸板。
(シュラって、カッコいい……)
ぼんやりとそんなことを思って、紫龍はたった今自分が感じたことに対して気恥ずかしさを覚えた。
(俺は、いったい何を……)
紫龍は頬が熱くなるのを自覚した。
慌てて寝返りを打って、シュラから顔を背ける。
シュラに背中を向けて、紫龍は眠ろうとして必死に努力した。そんなことをしても、返って神経が高ぶってしまって寝られない、ということにも気づかずに。
ドキドキと高鳴る鼓動は、しばらく速いリズムを打っていた。