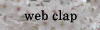悲劇的
――彼を愛している
そう気づいた時に、悲劇は始まったのかもしれない――
「サガ!」
照りつけてくるギリシャの太陽よりも眩しい笑顔が降り注いできた。
「どうだ、ちびっ子たちの様子は?」
尋ねてくる声に答えようと振り返るよりも先に、訓練着姿の少年たちが次々にアイオロスに駆け寄って行った。
「アイオロス!」
「兄さん!」
「うわ、お前たち、こらっ!」
サガとアイオロスは教皇シオンの命令で、先だって黄金聖闘士になったばかりの子供たちの面倒を交代で見ている。サガとアイオロスの二人が黄金聖闘士になったのは、5年前。まだ9歳の頃だった。
天秤座を除いて長く空席が続いていた黄金聖闘士だったが、サガとアイオロスが双子座と射手座の聖衣を授かったことを機に、山羊座、蟹座、魚座……と次々に揃い始めた。そして今年、ようやく12人の黄金聖闘士が全員揃ったのである。
まるで、次なる聖戦の訪れを告げるように。
そしてその予感をより強めるかのように、聖域の最奥にある女神神殿にはアテナの化身が降臨した。
「ちゃんとサガの言うことを聞いて練習したか?」
「もちろんだ」
アイオロスの問いかけに超然とした態度で答えるのは、ずっと目を閉じたままでいる乙女座のシャカだ。気安い、というのとはちょっと違う、どちらかと言えば上から物を見ているような口調で話す美しい金髪の少年は、神仏と対話する過程で小宇宙に目覚めたのだという。
「兄さん、俺こんなこともできるようになったよ」
アイオロスによく似た、太陽のような笑顔を見せるのはアイオロスの弟、獅子座のアイオリアだ。ほら見て、と言って無邪気な笑顔を浮かべたまま、アイオロスに向っていきなり光速の拳を繰り出した。
「ほぅ、拳の速度が上がったな。なかなかいいぞ、リア」
光の速さの拳をいとも簡単に全てかわして、アイオロスはアイオリアの頭を撫でた。
「あ、ずるいぞアイオリア。アイオロスー、俺のも見てくれよ」
「待てよ、ミロ。次は私だ」
「いや、俺が……!」
アイオロスがアイオリアの頭を撫でるのを見て、自分もー!と蠍座のミロと水瓶座のカミュ、牡牛座のアルデバランが我先にと争う。その輪から少し外れた場所で、教皇シオンが自ら育てた弟子である牡羊座のムウが穏やかな微笑をたたえていた。
彼らが来てから、聖域はすっかり賑やかになった。そして皆、アイオロスを兄のように慕っている。
「こら、お前たち。アイオロスが困ってるだろう」
助け船を出したのは、アイオロスの隣の宮である磨羯宮を守護する山羊座のシュラだ。アイオリアたちより少し年上で、サガやアイオロスの次に黄金聖闘士になった彼は、時々サガやアイオロスの手伝いをしてくれている。もっとも、ちびっ子たちがあまりにやんちゃすぎて、二人が手を焼くのを見るに見かねて……というのが事実だったりもするのだが。
「いい加減にしないと、斬るぞ」
「うわー、シュラ怖いーっ!」
お世辞にも目つきが良いとは言い難いシュラは、両手両足が大地を鋭利に切り裂くほどに研ぎ澄まされており、特にその右手は聖剣・エクスカリバーと呼ばれている。
「シュラも頼もしくなったなぁ。ここに来てすぐの頃は、よく俺やサガも手を焼いたもんだが」
「それはないだろう、アイオロス。俺はこいつらよりはマシだったはずだ」
アイオロスの言うとおり、シュラも相当やんちゃ坊主だった。ほぼ同時に聖域にやってきた蟹座のデスマスクや魚座のアフロディーテと3人していたずら三昧だったこともある。
そんな様子を見ながら思わず微笑すると、すかさずアイオロスから非難の声が飛んできた。
「こら、サガ。笑って見てないで手伝え」
「すまない、アイオロス。でも私よりもお前が相手をしてやった方が、彼らは喜ぶんじゃないか?」
「そんなことはないぞ、なぁ、ミロ?」
「うわ、やめてくれよアイオロス! 助けて、サガ!」
クセの強い髪をグシャグシャにかき回すアイオロスの手から逃れようと、ミロがサガに助けを求めてくる。その様子があまりに可愛らしくて面白くて、サガは思わず吹き出してしまった。
「あ、サガが笑った!」
「やはりサガは笑っている方がいいな」
「そうですね。サガはいつも眉間にシワが寄ってますから」
カミュの笑顔に呼応するように、シャカが微笑する。それを受けて微笑を深くしたのは、シオンの下で修業したムウだった。
「な、お前らもそう思うだろ? サガは笑ってる方が綺麗だよな」
太陽のような笑顔が、自分だけに降り注ぐ。
サガは知っていた。アイオロスの笑顔は、自分にだけ向けられる笑顔は、他の者たちが見ているものとは違って特別だ、ということを。
そして自分を照らす太陽の光が強ければ強いほど、闇が深くなるということも。
心の中にある闇が、蠢いて外へ出ようとする。
「そうか、ありがとう」
サガはそれを強烈な精神力で抑えつけ、笑顔を見せた。
「あー、やっと大人しくなってくれたか」
「今日も大変だったな。シュラが手伝ってくれたのと、途中でお前が来てくれたから何とかなったが。私一人ではとても手に負えなかった」
黄金聖闘士は本来は自分が守護する宮にいるものだが、今年聖闘士になった6人はまだ幼い。それ故に、白羊宮の下に広がる闘技場の脇にある宿舎で寝泊まりしていた。そこへ彼らを送り届けて、教皇の間へ行ってシオンに報告して、ようやくサガとアイオロスは解放された。
「そうか? でもお前だからあれくらいで済んでたんだぞ。俺だったらすぐ悪ふざけするからな、あいつらは」
「それだけ慕われているということだろう」
教皇の間から下りてくる間、双魚宮でアフロディーテが、磨羯宮ではシュラが二人に挨拶をしてきた。そしてアイオロスが守護している人馬宮へと下りてくる。
「じゃぁ、私はこれで……」
「待ってくれ、サガ」
そのまま自分の持ち場である双児宮へ下りて行こうとしたサガを、アイオロスが止めた。サガよりも少しだけ背の高いアイオロスが、背中越しに抱きしめてくる。
「まだ、ダメか?」
「アイオロス……」
アイオロスから好きだと告げられて、半年ほど経つ。
「サガ、俺はお前が好きだ」
日常会話の延長のように、満面の笑みを湛えながらそう告げられた時は、それが愛の告白だと気付けなかった。
恋人になってほしいという意味で好きだ、と改めて言われた時は、眩暈がしそうなほど歓喜した。まさか、片思いしていた相手から告白されるとは思わなかったのだ。それも、恋愛沙汰には縁のないように思われたアイオロスから。
あれから何度もキスを交わした。
だが、それ以上の関係は結んでいない。
サガが、あれこれと理由をつけて拒み続けているのだ。
「彼らの相手をして、少し疲れているんだ。明日も朝が早いし……」
「じゃあ、せめてお前からキスしてくれ」
「アイオロス……」
サガが考えもしなかったほど、アイオロスは積極的だった。臆面もなくサガに愛を告げ、体を、心を求めてくる。
サガはアイオロスの腕を外して彼と向き合った。身を乗り出して顔を寄せると、アイオロスが目を閉じてサガのキスを待った。
「お前が好きだ、アイオロス」
告げてから、サガはアイオロスにキスをした。ただ唇を触れさせるだけでは、アイオロスは納得しない。舌で唇をなぞり、口裂に差し入れてアイオロスの舌を探る。
深く長いキスをして、アイオロスはしぶしぶといった様子で納得した。
「おやすみ、サガ」
「おやすみ、アイオロス」
もう一度唇を触れ合わせて、サガはアイオロスから離れた。
双児宮へ帰りついたサガは、何者かに導かれるように鏡の前に立った。
心臓を鷲掴みにされて、握りつぶされるような痛みが走り、サガは思わず床に膝をついて喘いだ。
「くっ……ぅ……」
縋るように鏡に手を衝いて顔を上げると、自分の姿をそのまま映すはずの鏡には、違う人物が映っていた。
確かに、顔かたちは自分そっくりだ。だがその髪はサガが本来持っている青みがかった銀髪ではなく、夜の闇を移したような黒。そして瞳の色は血のように紅い。
それがもう一人の自分なのだと、サガにはわかっていた。
《お前が好きだ、などとよく言えたものだな》
「黙、れ……」
鏡の中に映る自分は、先ほどのアイオロスとのキスを嘲っていた。
《まだわからないのか? お前を愛しているのは俺だけだと》
「だが、私はお前など愛してはいない。私が愛しているのは、アイオロスだ」
《あんな男のどこがいい? この俺の存在も知らず、お前の上辺しか見ていないような男の》
もう何度繰り返したかわからない問答が続く。
《彼》が初めて出てきたのは、アイオロスを好きだと自覚した頃だった。鏡の中に映る自分の姿が違うものになって、サガを責めた。
「黙れ。お前などにアイオロスのことがわかってたまるか」
《何だと!?》
鏡の中の自分と言い争うのも、もう何度目になるかわからなかった。
《俺はお前、お前は俺だ。俺はお前が生みだしたもう一人の自分。その俺以上に、お前を愛する者などいるはずがない!》
声は、直接頭の中に響いてくる。割れそうなほどの頭痛がサガを襲う。
「く、あ……っ!」
サガは、鏡の前で気を失った。
次の教皇をアイオロスにする。
シオンからそう告げられたのは、ひと月後のことだった。
中国の蘆山・五老峰にいる天秤座ライブラの童虎と共に230年前の聖戦で生き残り、以来教皇として聖域を守り続けてきたシオンはもうかなり年老いている。
次の聖戦に向けて、若い者に聖域を継いでほしい。その時聖域を背負って立つのはアイオロスだと、シオンは告げた。
「おめでとう、アイオロス」
「ああ、ありがとう、サガ」
それから少しして、二人は人馬宮で向かい合っていた。
「どうした、あまり嬉しそうじゃないな」
「いや……俺よりもお前の方が相応しいんじゃないかと思うんだ。お前はリアたちだけじゃなく、ふもとの村の人たちにも慕われているしな」
「お前は教皇が判断を誤ったとでも言うつもりか? あの方の言われることに間違いはない」
「そういうわけじゃない」
サガの言葉を、アイオロスは即座に否定した。
「自信が、ないんだ」
「アイオロス……」
力なく項垂れるアイオロスを、サガは初めて見たと思っていた。
聖域の教皇になるということは、地上に降臨した女神アテナに次ぐ力を持つ、ということを意味する。88の星座を頂く聖闘士たちの頂点に立ち、アテナが不在の時は女神に代わって地上の全てを手に入れることになる、と言っても過言ではない。
それほどの重圧に耐え、かつそれを決して己の欲望のためには使わない、この世の平和と善のためにのみ使うのだ、という強靭な精神力が必要になる。
「教皇はお前を真に仁・知・勇を持った男だと認めて下さったのだ。ありがたくお受けするべきじゃないのか?」
「サガ……」
「お前が不安だというのなら、私がお前を支える。私は、お前なら立派に教皇として務めていけると思う」
サガの口を突いて出たそれは、まごうことない本音だった。
「だから、アイオロス……」
サガは背中越しにアイオロスを抱きしめた。
「サガ……!」
「っ!?」
次の瞬間、サガはアイオロスに強く抱きしめられて、その場に押し倒されていた。
「サガ、サガ……」
何度もサガの名を呼びながら、アイオロスがサガの体をまさぐりながら口づけてくる。
「アイオロス……」
サガは目を閉じて、アイオロスの口づけを受けた。そして自分に覆いかぶさってくるアイオロスの背中に腕を回した。
サガに変調が訪れたのは、人馬宮を出て自宮へ戻ってからすぐのことだった。
初めて男を、アイオロスを受け入れた衝撃がまだ残っている身体を、アイオロスに貫かれた時以上の、今までにない激痛が襲った。
(ダメ、だ……)
気を失ってはいけない、ととっさに判断して自制心を保とうとするが、叶わなかった。
《あんな男にこの体を抱かせたお前が悪いのだ》
(どうする気だ!?)
《決まっている。殺すのよ、あの男を!》
(やめろっ!)
《これでお前は俺だけのものになる。未来永劫、俺だけのものにな!》
もう一人の自分が、自分の中から出て行こうとするのをサガは感じていた。
《ついでに、お前を教皇に指名しなかったあの無能な老人も殺してやる。そしてまだ赤子のアテナをも殺せば、俺たちが地上の神となる!》
(!?)
先ほどアイオロスに抱かれながら歓喜した以上の激情が、サガの内から溢れてくる。
《お前は大人しく見ていろ。あの男が、無能な老人が、力のない赤子が死んでいくのをな!》
(やめろぉっ!)
叫び声を上げようとした時、サガは自分の意志が無理やり抑えつけられるのを感じた。抗おうにも抗えないほどの強い力で。
遠のいていく意識の中で、ふとアイオロスの笑顔が浮かんだ。
太陽のように、闇を照らす笑顔を。
(アイオロス……逃げて、くれ……)
祈るように思いを紡いだ次の瞬間。
サガは、完全に意識を断ち切られた。
目が覚めた時には、全てが終わっていた。
サガは、教皇の間でマスクをつけ、血塗られた法衣を身に着けていた。
「これは……まさか!」
足下に、血のついた黄金の短剣が落ちているのが目に飛び込んできた。掌に、その柄を掴んでいた感触が残っている。
「殺してしまったのか、本当に!?」
身を引き裂くほどの罪悪感がサガを襲う。
身に着けている法衣は、背中から腹に向って穴が空いている。右手には、何者かの体を貫いた感触もあった。
「お前は……教皇を、あのシオン様を殺したのか!?」
《そう騒ぐな。あんな老人を始末するくらい、大したことではない》
「なんという恐ろしいことを……」
《だがこうなった以上、お前は教皇として生きるしかない。幸い、あの老いぼれは顔をマスクで覆っていて誰も素顔を知らないからな。成り済ますなど、お前にとってはわけもなかろう》
頭の中で声が響いた時、教皇の間に入ってくる者がいた。
「教皇」
黄金聖衣に身を包んだ、山羊座のシュラだった。
「逆賊アイオロスはこのシュラが成敗しました。ご安心下さい」
「っ!?」
頭のパーツを取って脇に抱え、跪いてそう告げるシュラの言葉に、サガは息を呑んだ。
(逆賊、だと!? アイオロスが!? どういうことだ……?)
動揺している表情は、マスクに隠されてシュラに悟られることはなかった。
「御苦労だった、シュラ。宮へ戻るがよい」
「はっ」
言葉が、自分の意思とは関係なく口から零れ出ていった。もう一人の自分がやっているのだと、サガはおぼろげに理解した。
シュラは頭を下げて、立ち上がった。踵を返して出て行こうとするシュラを、もう一人の自分が呼び止めた。
「シュラよ」
「はっ」
「逆賊アイオロスの死体はどうなった?」
「それは……」
尋ねられたシュラが、らしくもなく言い淀んだ。
「答えられぬのか?」
「いえ。アイオロスは私のエクスカリバーを受けて、聖域の谷底へ落ちました。この闇夜では、どこへ落ちたのかも確認することは叶わず、戻って参りました。明日、夜が明けましたら探索を開始します」
シュラの言葉に、サガは少し安堵した。
アイオロスほどの男ならば、シュラの一撃を受けて谷底へ落ちたとはいえ、きっと生きている。サガはそう確信した。
「そうか、ならば……」
必ず見つけて、もし息があるようならば止めを刺せ。
そう言わせようとする意志を、サガは全身全霊で抑え込んだ。
「捨てておけ」
「は?」
「谷底へ落ちたのなら、アイオロスほどの男といえど助かるまい。呼び止めてすまなかった。もう下がってよい」
「はっ。失礼仕ります」
シュラは再び頭を下げて、今度こそ教皇の間を出て行った。
足音が遠ざかり、聞こえなくなった時。サガの頭を激痛が襲った。
「くっ……」
《何故邪魔をした!? アテナ共々殺せたものを!》
アテナが短剣で刺される寸前にアイオロスによって救われ、連れ出されたことはもう一人の自分に残る記憶で知らされた。
「お前の思い通りには、させん」
《どういうつもりだ!? 禍根を断っておかねば、お前も俺も滅ぶことになるんだぞ》
「滅んでしまえばいいのだ、お前ごとな」
《バカな!?》
「アテナが生きておられるのなら、いつか私たちを断罪するために戻ってこられるだろう。お前も私も、それまでの命だ」
サガは顔を覆っているマスクを外した。
そのマスクを、涙が濡らす。
祈らずには、いられなかった。
(頼む、生きていてくれ。アイオロス……)
その日以降、聖域から双子座のサガの姿が消えた。
射手座の聖闘士だったアイオロスは逆賊として聖闘士だった証を剥奪され、射手座の黄金聖衣も消え、人馬宮は無人の宮となった。
アイオロスを成敗した山羊座のシュラの表情からは笑顔が消え、シオンの弟子だった牡羊座のムウの姿も聖域から消えた。
アイオロスとサガ、二人の年長者を囲んで黄金聖闘士たちが笑い合う姿は、二度と見られることはなかった。
消息を絶ったように見せかけたサガは。
シュラとデスマスクとアフロディーテに真実の一部だけを明かして味方につけ、偽りの教皇として聖域をまとめ上げた。
そして、待ち続けた。
女神の手によって、自分を断罪するために、運命のハンマーが振り下ろされる日を。
Fin
written:2008.05.11
というわけでお届けしました、ロス×サガでサガの反乱前後のお話です。
このお話、マーラーの交響曲第6番「悲劇的」を聴いて思いつき、ザザッと4時間くらいかけて書き上げました。
タイトルがタイトルなので、こういうお話になってしまいました(汗)
この手の話は十数年前、コミケなどでも★矢が全盛期だった頃にいろんな人が書いておられたと思います。それらは自分の中にも蓄積されていると思うのですが、自分なりに書いてみたらどうなるんだろう?と思ったのです。
また、最近「冥王神話 LOST CANVAS」を全巻読みまして。あのお話って、もしサガが反乱を起こしていなくて、黄金聖闘士たちが全員揃った状態でハーデスとの聖戦を迎えていたら……という、もう一つの可能性を示して下さっているようにも思うのですね。
そんなこんなもあって、自分の頭の中を整理する意味も込めて、書きました。
ちゃんと書いたら、もっと長くなってしまうお話だろうと思ったので、あえて淡々と事実だけを述べる形で書いたのですが(苦笑)
ちなみに、お話のモチーフとなっているマーラーの交響曲第6番。
最終楽章で、本当にステージ上には大きなハンマーが登場します。そしてその大きなハンマーを振り下ろす、という効果音が入ります。音だけ聴いていると、ちょっとわかりにくいんですけどね。
なので、「運命のハンマーが…」云々という記述が出たんですが。
あのハンマー、女性が振り下ろすには大きいし重いんじゃない?と、自分で自分にツッコミを入れたのは、ココダケのお話です(笑)