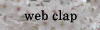※注:このお話は「ク・ドゥ・クール」の1年後という設定で書かれております。シュラも紫龍も聖闘士ではなく、オリジナル設定での人物として描いております。この二人は聖闘士じゃなきゃ!というお方様は取扱いにご注意くださいませ(礼)
Adajio
紫龍はいつものように、シュラが用意した座席に座っていた。
1年ぶりのアテネ。
このホールに入るのも、ちょうど1年ぶりだった。
あの時は男娼とその客だった紫龍とシュラの関係は、この1年間でかけがえのない恋人同士へと変化した。今ではもう、お互いのいない人生など考えられないほどに。
男娼と客として出会って、3度の逢瀬を重ね、もう二度と会うこともないだろうと諦めていたあの日。紫龍はシュラの親友の一人であるアフロディーテの導きでシュラと再会した。
その時に座った、ステージ上手側の奥の席に紫龍はいる。ステージの奥から、斜め前方にシュラを見る席に。
前半は、ソリストを迎えての協奏曲だった。
地元アテネ出身の若手ヴァイオリニスト、アイオリア。兄であるアイオロスもまた、世界各国で活躍する音楽家――こちらはチェリストなのだが――であり、兄弟揃ってプロとして活動しているのだ。
金色の髪と、精悍な顔つき。
身長が高く体格も良い彼は、軽々とハチャトゥリヤン作曲のヴァイオリン協奏曲を弾きこなして見せた。現代音楽風の、リズミカルで超絶技巧も織り込まれている難曲を。
シュラは、完全にサポート役に徹していた。
ソリストであるアイオリアを立て、自分は前に出て行かない。カーテンコールで挨拶をする時もアイオリアだけを前に立たせて、自分は第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの間に立ってオーケストラの中に埋もれていた。
休憩を挟んだ、後半。
ここからシュラは本領を発揮する。
サポートしなければならない相手はいない。シュラが全てを支配し、統率する時間がやってくる。
後半のプログラムの1曲目に演奏されるのは、バーバーというアメリカの作曲家が作った『弦楽のためのアダージョ』。紫龍が聴いたことのない曲だった。
スペイン国内でコンサートを振る時も、国外で振る時も。
常に紫龍を伴って、リハーサルから同席させるシュラなのだが、今日のコンサートだけは紫龍の同席を許さなかった。本番前に行われる最終リハ、ゲネプロにも立ち会わせてもらっていない。だから、どんな演奏になっているのか、紫龍は全くわからない。
曲そのものも、プログラムによれば有名な曲らしいのだが、紫龍は初めて聴く曲だった。
今日は、俺とお前にとって記念すべき日だからな。
客席で見守っていてくれ。
いつものように。
シュラにそう言われて、従うことに否はない。
ステージに大小さまざまな弦楽器を持った演奏者が登場してきた。
パラパラと拍手が飛ぶ客席が少し暗くなって、ステージの明かりが強くなる。
黒いドレスやスーツに身を包んだ演奏者たちが、それぞれの席に座る。最後にヴァイオリンを持ったスーツ姿の男性が現れて、客席からの拍手が少し強くなる。彼は客席に一礼して、指揮者に最も近い場所にある空席に座った。
そして一呼吸置いて、黒いスタンドカラーのスーツに身を包んだシュラが袖から現れた。客席からの拍手がひと際強くなる。
紫龍もシュラに拍手を贈った。
客席に深く頭を下げて、シュラが指揮台に上がる。
指揮棒を構える直前、シュラはふと目線を上に流した。紫龍が座っている場所へと。
一瞬、シュラと目が合った。
お前のために
再会したあの時、ホールのロビーでシュラが言った言葉。
コンサートの度に、いつもシュラが口にする言葉。
(俺はお前のために振る)
唇は動かなくても、シュラの言いたいことは視線を合わせただけで伝わってくる。
シュラが自分のために振るというのならば。
紫龍は全身全霊を、彼が紡ぎだす音に傾ける。
紫龍の姿を確認して、紫龍が身構えるのとほぼ同時に、シュラは指揮棒を構えた。自分の前で、タクトを真っ直ぐに立てるように。
一瞬にして、シュラの周囲の空気が変わる。
研ぎ澄まされたような緊張感が、彼の周囲に漂う。
そしてその空気は、弦楽器のみで構成されたオーケストラも、客席も、ホール全体をも包み込んでいく。
客席のざわめきが納まるのを待って。
シュラは静かに指揮棒を動かし始めた。
静寂の中から音が生まれるように、密やかな音がホールに満ちる。
弦を擦る弓の圧力と、スピード。それらを絶妙にコントロールして、ひっそりと囁きかけるような音を演奏者たちが生み出していく。
シンプルで、美しくて、でも切ないメロディがホールに広がる。
弦の音が折り重なり、ヴィブラートが漣のように心を打つ。
音の重なり方を変え、和音を変え、音量を次第に上げながら繰り返されるメロディ。
高揚していくようで、けれどまだ抑圧されている音。
(……っ?)
折り重なる弦楽器の音の中に、紫龍は異質な音を聴いた。
シュラの、声。
曲に表情をつける左手で抑制をかけつつも、しっかり歌わせようとするシュラが、その心の現れとして思わず出てしまった声が、曲の合間から聞こえてくる。
(シュラ……)
ヴァイオリンの音が高みに登っていく。
音量も高まって、頂点を極める。
高音で伸ばされる音に、絹糸で心臓を絞られるような、苦しさが混ざったような切なさを覚える。狂おしいほどに求めてくる音に、全身を支配される。
知らず浮かんできた涙で、ステージにいるシュラの姿が霞んだ。
やがて、曲はもう一度初めのメロディを静かに繰り返す。
そしてそのメロディも切れ切れになり、再び静寂の中に沈むように曲が終わる。
曲が終わり、シュラが指揮棒を下ろしても、客席には静寂が漂っていた。
ほう、とため息を吐くような音があちこちから漏れて。
客席は拍手で溢れた。
紫龍も、シュラが動くのを見て、ようやく詰めていた息を吐いた。
完全にシュラに釘付けになっていた。全身全霊が。
(やっぱり、貴方は凄い)
周囲に倣って、客席に頭を下げるシュラに拍手を贈る。
その頬を、一筋の涙が伝い落ちた。
終演後、紫龍は少し時間を置いて楽屋に向かった。
セキュリティが厳しくなっている昨今、入場許可証がなければ楽屋には入れない。紫龍はシュラから受け取っていた許可証を見せて、楽屋が並ぶ廊下に入った。
ドアの開いているシュラの楽屋を見つけて、声をかけた。
「シュラ……っ!?」
そっと中を覗くとほぼ同時に、紫龍はシュラに抱きすくめられていた。
「遅かったな。待ちくたびれたぞ」
シュラは汗に濡れたスーツを脱いで、黒いシャツ姿に着替えている。けれどまだ汗が完全に引いていない彼の体から漂う汗の香りが紫龍の鼻をくすぐる。
「……っ!」
紫龍のためにと捧げられた極上の音楽によって高められた感性が、敏感に反応する。
抱き締められたその一瞬で、紫龍は欲情した。
「おかげで、アイオリアに付き添っていたアイオロスの長話に付き合わされるハメになった」
抱きしめたまま耳元で話すシュラの声が、普通に話しているだけのその声が、官能的に響く。
「……貴方は、凄い。でも、ズルい人だ……」
吐息と共に吐き出す声の熱さを、紫龍は自覚した。
密着したこの距離で、誰よりも肌に馴染んだ愛しい相手に隠せるはずもない。
自分が、どうしようもなく欲情していると。
「紫龍? ……お前は――……」
訝しげに呼びかけたシュラは、案の定すぐに紫龍の変化に気づいた。
吐息だけで微笑して、抱き締めていた腕が片方だけ外れて、紫龍の頬を柔らかく包む。
「Adagioは、それほど官能的に聞こえたか?」
そういう曲ではないんだがな、本来は。
そっと囁くシュラの声が、紫龍の口腔に消える。
優しく唇を塞がれて、けれどもそれだけでは足りず、すぐに紫龍から深く口づけた。
シュラの舌を求めて口裂を割り、口腔を探る。
同時に、紫龍は右手をシュラの下肢に伸ばしていた。まだ変化の兆しのないそこに、ズボンの上から手を這わせて刺激を加える。
「そんなに欲しいか、俺が?」
「欲しい。貴方の全てが」
紫龍の手の中で、シュラの熱が育ってくる。
「そんな風に求められたら、たまらないな」
キスの合間に囁いて、シュラは紫龍から主導権を奪った。
紫龍の口腔を深く探り、舌を絡ませながら、楽屋に置かれたソファに紫龍を押し倒した。
「んっ……ふ――……っ」
性急にシャツの上から紫龍の体をまさぐり、ズボンのベルトを外して下着の中に手を差し入れる。猛り始めている紫龍の熱に直に触れると、ビクリと全身が跳ねて快感を訴える。
「シュラ……早、く……」
初めての情交を思わせる性急ぶりで、紫龍がシュラを求めてくる。
シュラが紫龍に手淫を加えると同時に、紫龍もまたシュラのパンツの中に手を潜り込ませて、シュラの昂りに触れていた。掌で撫でるだけでは物足りず、幹をしごいて先端に指を這わせて腹で擦ってくる。
シュラも紫龍も、先端から蜜が溢れ出すまでにそれほど時間はかからなかった。
「紫龍……俺もお前が欲しい。俺の音を聴いて、感じたお前の全てが」
耳元で囁くシュラの声も、熱く濡れている。
その声だけで、どうしようもなく感じてしまう。
紫龍はシュラの頭を引き寄せて、深く口づけた。
「――っ! んぅっ……――っ!」
同時に秘所に熱の塊が押し込まれてきて、少しの痛みを伴う強烈な圧迫感に襲われる。男に抱かれ慣れた体といえど、ほとんど馴らしていない状態での挿入はそれなりに負担がかかる。
それでも、今すぐにシュラが欲しかった。
もっと、ずっと奥まで……
自分からも腰を動かして、シュラを奥へと引きずりこむ。
「ん……ふ、――……ぅんっ」
唇を塞がれたまま、シュラが激しく腰を打ちつけてくる。
何度も、何度も。
必死で抑えつけながらも、決して隠すことのできない激しさが溢れだしていたあのAdagio。その抑制から解き放たれて、激しい劣情に駆り立てられるままに、紫龍を貪る。
喘ぎも吐息も、全てシュラの口腔に飲み込まれた。
「んっ、んぅっ――っ、んぁ……っ!」
二人が繋がる場所から、粘液の絡まる音が。
シュラが腰を打ちつけるたびにぶつかる肉の音が。
ソファが軋む音が。
舌を絡ませ合う音が。
二人の吐息が。
官能に彩られた濃密な音が満ちて、重なり合って昂っていく。
「ん……っ、シュラ、もう――……っ!」
内襞を抉るシュラの陰茎が感じる場所に当たるように、自分からも腰を揺らしていた紫龍が、唇の離れた隙に限界を訴えた。
いつものように時間をかけてゆっくりと味わう余裕もなく、ただ体を繋げて解放を求めていたシュラも、己の熱が限界まで膨れ上がっているのを感じていた。
だが、このままでは……
お互いに汚れた体を清めることのできるものは、ここにはない。
シュラは咄嗟に紫龍の中から己を引き抜いた。
「ん……っ、シュラ……?」
絶頂を極める直前で放り出された紫龍が、不満げに呼びかけてくる。
シュラは体勢を入れ替えて、先端から涙を零しながらそそり立つ紫龍の牡を口に含んだ。
「あっ……ん――……っ」
濡れた熱い口腔に飲み込まれる感触に、全身が泡立つような快感を覚える。それはシュラに最奥を抉られるのとはまた違った快楽だった。
目の前に、たった今まで紫龍の中を荒らし回って、眩暈がするほどの快楽を与えていたシュラの牡が晒されている。
紫龍は夢中でそれにむしゃぶりついた。
「ん……む、ふ……んっ」
口腔深く飲み込んで。
吸い上げて。
舌を先端に絡ませて。
相手が加えてくる口淫に呑まれそうになりながら、お互いに相手の熱を愛する。
「ん――……っ、ん、んぁ……っ!」
ひときわ強く吸い上げられて、紫龍が己を手放した時。
シュラもまた、紫龍の口腔に欲望を吐き出していた。
Fin
written:2008.11.26
というワケで、久方ぶりの山羊龍です。
この話、書くきっかけになったのが2008年11月22日に開かれた「聖響/音楽至上主義 第4回」(コンサートの詳細はMusic別館 Allegro con brioをご覧くださいませ)の直後でした。
コンサート終了後、奇しくも同じ日に大阪入りしていた方たちと紫龍受け友の会プチ関西支部会を開きまして。二次会でスケブ交換会を行い、その際に書かせていただいたものをきっちり完成させてみよう、ということでこうなりました。
おかしいなぁ。
この曲、こういう曲じゃないんだけど(笑)
エロになったのは多分、相手が山羊さまだからだわ(爆)
それと、関西支部会でエロトークが出た影響だわ(笑)
「結月さんのトコの三ツ星エロが読みたいよね」なんて話をチラッと聞いてしまったからだわ(笑)
でも、こういう話が浮かんだのも全て。
聖さまが素晴らしい演奏をしてくださったおかけですので、紫龍受けスキーな皆様、聖さまに感謝して下さいませね♪(←違っ;)
こういう話のネタにしてしまいましたが、バーバー作曲の「弦楽のためのアダージョ」はとても素晴らしい名曲です。
私的には涙なしには聞けない1曲であります。
よろしければぜひ、一度聴いてみて下さいませ(^.^)