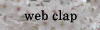sweet trap
麗らかな初夏の午後。
紫龍は双魚宮の脇にある薔薇園にいた。
聖域の中心にあって、12人の黄金聖闘士によって守られる12宮の最後の宮である双魚宮には、代々魚座の黄金聖闘士が育てている薔薇園がある。
魚座の聖闘士は猛毒の薔薇や、人の血を吸う薔薇など、さまざまな種類の薔薇を使って闘うという華麗な戦法を取る。そしてそれを操る聖闘士自身も、代々見目麗しい者が選ばれる。
現在この双魚宮を預かっているアフロディーテも、その例に漏れずまさに花のような美しさを誇っている。
紫龍は薔薇園でそのアフロディーテが淹れたローズティーをご馳走になっていた。
「凄い、満開なんですね」
「ああ。薔薇は年に2回花を咲かせるからね。手入れは大変だけど、手をかければかけただけ、彼らは美しい花を咲かせてくれるんだよ」
紫龍に話しながら、アフロディーテは切り取ってテーブルの上に飾った艶やかな深紅の薔薇の花びらを撫でた。
「ここに咲く薔薇には毒はない。まぁ、毒薔薇ばかりではさすがの私たちも飽きてしまうからね」
先代までは毒薔薇を育てることに専念していたらしいのだが、アフロディーテが個人的な趣味で毒のないさまざまな種類の薔薇を育てることにしたらしい。紫龍が案内されたのは、普通の薔薇を育てている薔薇園の一角にある露台だった。そこには日除けの屋根がつけられ、4人掛けの丸テーブルと椅子が置かれている。椅子もテーブルも繊細な模様の入った造りになっていて、薔薇園の雰囲気によく溶け込んでいる。
「このローズティーもアフロディーテが?」
「ああ。といっても、普通の紅茶に乾燥させた薔薇の花弁を入れただけなんだけどね」
茶葉の香りが強すぎず、花の香りが程良く漂って口腔に広がり、鼻腔をくすぐる。
「それで? 君が私を訪ねてきた理由をまだ聞いていなかったな」
アフロディーテも優雅な手つきでティーカップを口に運び、紅茶を味わう。花が綻ぶような微笑を浮かべて尋ねると、紫龍は少しだけ緊張を解いた。
「私に訊きたい事があるって?」
「ええ、はい……」
しかし、紫龍はすぐに緊張した面持ちに戻ってしまう。
「何を訊きたいのかな? 私に答えられることならば、何でも答えよう」
この龍星座ドラゴン紫龍は、女神アテナを奉じて一度はアフロディーテと敵対したことがある。青銅聖闘士でありながら黄金聖闘士を倒し、女神の血を受けた聖衣をオリンポス12神のみがまとうことを許された神衣の域にまで高め、冥王ハーデスを倒した英雄たちの一人でもある。
艶やかな長い黒髪、やや細身の体格、あまり日に焼けない肌理の細かい肌。
だが、彼は龍の化身であり、その右腕にはアフロディーテの親友である山羊座カプリコーンのシュラから授けられた聖剣エクスカリバーが宿っている、というれっきとした聖闘士だ。彼の師匠である天秤座ライブラの童虎が彼に天秤座の黄金聖衣を譲る日も近い、と聖域で噂される人物でもある。
そして何よりも。
彼は、シュラの恋人だ。
彼自身の礼儀正しく義理堅い性格に惹かれることもあって、アフロディーテは紫龍を気に入っている。
その彼から、緊張した面持ちで訊きたい事があるから時間を取ってほしい、と言われてアフロディーテは二つ返事で頷いた。そして香水のような嫌味のない、自然な薔薇の香りに満たされた中ならば紫龍の緊張も解けるのではないか、とこの薔薇園に案内して紅茶を淹れた。
「真面目な質問でも、ちょっとHな質問でも。他でもない君の頼みならば、何でも聞くよ?」
アフロディーテは紫龍に柔らかい視線を向けた。
「はい、ありがとうございます」
低く深みのある紫龍の声が心地よく耳に響く。
アフロディーテは彼が話し始めるのを待ちながら、そっと紫龍の様子を伺った。フランス風の庭園、それも薔薇に囲まれたこの庭園の中にあって、決して埋もれることのない凛とした美しさを誇る東洋の花。
(アイツの趣味の良さには呆れるな)
アフロディーテは思わず、心の中で親友に向って毒づいた。
「では、お言葉に甘えて……。あの、アフロディーテはデスマスクと付き合っているんですよね?」
「ああ、今はね。何せシュラのヤツは、君と出会ってからすっかり君一筋になっちゃったからな」
どうせいつかはバレるのだから、とアフロディーテは紫龍がシュラと恋人同士になってから間もなく、自分がシュラとデスマスクの二股をかけていたことを話してしまっている。いや、二股というのは少し語弊がある。もともとデスマスクとは何となく心も体も通い合っているような関係だったのだが、シュラとはセックス・フレンドのような割り切った関係だった。
「付き合っているということは、当然、その……エッチもするんですよね?」
余程口にするのが恥ずかしいのか。
エッチ、の部分だけ消えそうなほど小さい声で発音する紫龍が可愛らしくて、アフロディーテは思わず頬が緩んだ。
「そうだね。私もデスも、今はアテナのお力で18歳の若々しい肉体を持っているわけだし。精神的にはそれなりに成熟した男性だからね。恋人という関係にある以上、プラトニックで済ませるわけにはいかない。当然セックスだってするよ」
「そう、ですよね」
「君とシュラだってそうだろう? 君はまだ若いけれど、シュラはもう成熟した大人なんだから」
「それは、そうなんですけど……」
そこまで話して、アフロディーテには紫龍が訊きたい事の内容が、大筋で見えたような気がしていた。つまり、セックスに関する悩み事があって、誰かに相談に乗ってほしかった、というわけだ。内容が内容だけに、彼の師匠である童虎に話すわけにはいかない――というか、彼をここまで純粋培養したのは、他でもないその童虎なのだ。他に誰か……と考えて、アフロディーテという結論に至ったというわけだろう。
「それで? シュラとのセックスに不満がある、とか?」
「そんな! そういうことじゃ、ないんです」
カマをかけるつもりで口にした問いかけは、即答で否定された。
当人は無自覚のようだが、とんでもないノロケを聞いたものだとアフロディーテは心の中で苦笑した。
「シュラとのセックスに満足してるなら、君が訊きたい事は何だい?」
「アフロディーテは、週に何回くらい、その……してるのかな、と……」
俯き加減で問うてくる紫龍の頬が朱に染まっている。
「デスと? そうだな、だいたい週に2回から3回ってトコかな。たまに、私がわざと焦らして1回ってこともあるけどね」
「そう、ですか……」
アフロディーテが答えると、紫龍はまた沈黙した。
(これは……私が聞き出してやらないとダメかもしれないな)
後から知って驚愕したのだが、紫龍はまだ14歳だ。しかも、修行地である五老峰では身の回りの世話をする少女と同居していたにもかかわらず、全く手を出そうともしなかったという堅物でもある。そんな彼の蕾を文字通り花開かせて、甘い恋の蜜の味を教えたのだ、あの親友は。
恋を知ったばかりの初心な処女では、こういう話題で恥じらうのも無理はない。
アフロディーテは腹を括った。
「君はどうなんだい? シュラとは週に何回くらいセックスしてるの?」
「俺は、その……」
「?」
「ほぼ、毎日というか……たまに、1日何もしないこともあるんですけど、その次の日には必ず、シュラが……」
「セックスを求めてくるわけだ?」
「はい」
これはまた、とんでもないノロケ話を聞かされたな、とアフロディーテは苦笑した。
もともとシュラは性欲が強い方だ。そして紫龍は、特定の相手を持たなかった彼がようやく得た「恋人」でもある。ほぼ毎日恋人を求めることは想像に難くなかったのだが。
(まさか、ホントに毎晩ヤってるとはね)
シュラの体力にも呆れるが、それに付き合っている紫龍も大したものだ、とアフロディーテは思わず感心した。
「まさに蜜月ってことだね。いいことじゃないか」
「そうでしょうか」
「おや、不満でもあるのかな? 毎日シュラに愛されているっていうのに」
「シュラにされるのは、全然嫌じゃないんです。むしろ、嬉しいと思うんですけど、でも……」
「でも?」
「ああいうことって、そんなにまでしなければいけないことなのかな、と思うんです。俺はただ、シュラの側にいられるだけで嬉しいし、幸せだと思うのに」
話しながら、紫龍はティーカップに視線を落とした。琥珀色の水面が、二人の間を隔てるテーブルの微妙な振動で揺れる。
アフロディーテは、紫龍の口から次々と飛び出すノロケとしか言いようのない言葉の数々に頭を抱えそうになった。
(まったく、アイツは……)
「それは、私がどうこう言う問題じゃないな。ちゃんとシュラと話し合うんだね」
「はい……」
「ただ、シュラは性欲が強いというのは事実だからね。初恋で相手にするには大変な相手だってことは認めるよ。だけど、お互いに求め合っているんだから、それでいいんじゃないかな?」
煮え切らない様子の紫龍にそう言って、アフロディーテはローズティーを口に含んだ。
「それが、その……」
「ん? まだ何か問題があるのかい?」
「お互いに求め合う、とアフロディーテは言いましたけど。それが……」
「うん?」
再び言葉を濁す紫龍に、アフロディーテは思わず首を傾げた。
「俺は、その……いつもシュラに求められてばかりで、自分からシュラに、その……抱いてほしい、とか言ったことがないんです」
「……」
アフロディーテは、不覚にも思わず口腔に広がる薔薇の香りにむせてしまいそうになった。
「だから、それでいいのかな、と……」
紫龍の口から飛び出す言葉に、アフロディーテは文字通り頭を抱えそうになった。
(シュラ、あの男は!)
アフロディーテはこの場にいない親友を、心の中で罵った。
紫龍のこの反応を見ただけでも、あの男がどれほど彼を大事にしているか、言葉よりももっと雄弁に語って聞かされているような心地だった。
しかし、何よりも問題なのは……
(この子ってば……)
「まるでわかってないんだな、君は」
アフロディーテはため息交じりに呟いた。
「え?」
「君、さっき言ったよね。シュラとは毎晩のようにセックスしてる、って。それもいつもシュラから求めてくるって」
「あ、はい……」
そろそろ慣れてきたのか、紫龍は赤面することもなく普通に頷いた。
素直な反応に気を良くしながら、アフロディーテは紫龍に教えてやることにした。これほど純粋培養されている上に、シュラにこの上なく大事にされているこの子は、誰かが気付かせてやらなければ自分からは絶対に気づかないだろう、そう思った。
「そんな毎晩シュラに求められていたら、君から求める余裕なんてないだろう。別に、君が気に病むことじゃないよ」
「そう、ですか?」
「それにね、君だって求めてきたシュラにちゃんと応えてるんだろう? だったら、それでいいんじゃないか」
「はい……」
それでも、紫龍からはまだ不満そうな表情が消えない。
「それとも何だい? そんなに自分から誘ってみたいのかな、君は?」
「誘うって、そんな……」
「性欲っていうのは特別なものじゃない。誰だって普通に持ってる本能だよ。食欲や睡眠欲と同じでね。誰よりも愛する恋人に抱いてほしいって自然な欲求を伝えることも、別に恥ずかしいことじゃないだろう?」
「そう言われると、そうかもしれない……」
納得しかかっている紫龍に、アフロディーテは極上の微笑を浮かべて見せた。
「そのうち、シュラが何も言わないこともあるだろう。その時に、君がシュラに抱いてほしいと思ったら、素直にそう言えばいい」
そして、アフロディーテは紫龍に向ってウィンクをして見せた。
「でも、どう言えば……?」
「それは自分で考えることだね。私が知恵を貸すことじゃない。でも、シュラは君よりずっとオトナだし、そういう場面には慣れてる。それに誰よりも君を愛している。だから、君の思いには必ず気づくだろうし、どんなものでも受け止めてくれるよ」
「わかりました。ありがとうございます」
紫龍は頷いて、カップに残っていたローズティーを干した。
アフロディーテにローズティーをご馳走してもらってから、しばらく経った秋の夜だった。
一応自分の寝所が用意されている女神神殿でもなく、師匠である天秤座の童虎がいる天秤宮でもなく。紫龍は磨羯宮でシュラと寝床を共にすることが多くなっている。それはもう、ほとんど同棲していると言ってもいいほどに。
その夜も、先に風呂に入らせてもらった紫龍は、風呂から上がってきたシュラが隣へ潜り込んでくるのをベッドで待っていた。以前は酒を飲んで夜更かしをすることが多かったシュラだが、紫龍と共に過ごすようになってからというもの、紫龍に合わせて休む時間が早くなっている。
「おやすみ、紫龍」
「おやすみなさい、シュラ」
シュラは紫龍の額に軽くキスをして、そのまま横になった。紫龍の唇に触れることもなく、紫龍に背を向けて寝入ろうとしている。
(シュラ……?)
紫龍はTシャツ越しにシュラの背中を見つめた。
紫龍より肩幅が広く、鍛え上げられた背筋が盛り上がる背中。紫龍よりずっと体格が良くて、頼もしい背中が、肩が、呼吸に合わせて動く。
(何もしない、のか……?)
一昨日の夜は、今のように何もせずに二人で並んで眠った。
昨夜はシュラに求められて一度セックスをして、それから眠っている。だから、切羽詰まるほどどうしてもセックスしたいと思う……要するに溜まっているという状態ではない。けれど……
何となく、寂しい。
シュラが寝台に入ってくるまで、今夜もまた求められることを心のどこかで期待していた。けれどシュラは……何もせずに眠ろうとしている。
「シュラ」
思わず、呼びかけた。
「ん? どうした、眠れないか?」
呼びかけると、シュラは寝返りを打って紫龍の方を向いてくれた。そして気遣うような優しい声で問いかけてくる。
「そういうわけでは……」
「呼んでみただけか」
口ごもる紫龍に、シュラは軽く苦笑した。
「違うんだ。ごめんなさい」
眠ろうとしていたシュラを邪魔してしまった、という罪悪感が紫龍の中に広がる。
「謝らなくていい」
苦笑を深くして、シュラは紫龍を抱き寄せた。
紫龍より体温の高い、厚い胸板が規則正しく上下するのを布越しに頬で感じる。指を滑らせるように髪を撫でる手が、心地いい。
少しの間そうされているだけで、体が熱くなってくる。別にシュラは何をしているわけでもないのに。ただ抱き寄せているだけなのに。
もっと、シュラを感じたい。
(そのうち、シュラが何も言わないこともあるだろう。その時に、君がシュラに抱いてほしいと思ったら、素直にそう言えばいい)
アフロディーテに言われた言葉を、紫龍は思い出した。
紫龍はシュラに体を擦り寄せた。
「紫龍?」
問いかけるように呼ばれて顔を上げると、シュラは少し困ったような表情をしていた。
(もしかしたら……)
紫龍は直感した。シュラも、本当は自分を抱きたいのかもしれない。抱きたいけれど、紫龍を気遣って我慢しているのかもしれない、と。
困ったような表情をしているシュラも、愛しいと思った。
けれど、抱いてほしいと言うのは、まだ少し抵抗がある。
「シュラ……」
「っ!?」
紫龍は身体をずり上げて、シュラの唇にそっと自分のそれを触れさせた。初めは軽く触れ合わせただけで、すぐに離す。そしてシュラがいつも紫龍にするように、口裂から舌を差し入れていく。
頬の内側を、上顎を何度も舐めて、舌を絡ませて、シュラの口腔を愛撫する。
紫龍は途中でシュラが何か仕掛けてくるのを待った。が、シュラは紫龍にされるがままで、自分からは何もしてこない。
少し困って唇を離すと、シュラは苦笑したような、けれどどこか嬉しさを隠せない様子で紫龍を見下ろしてきた。
「こんなキスをして……俺が我慢できなくなったらどうする?」
「しなくてもいい、と言ったら?」
「紫龍!?」
「あなたと、したい……です」
シュラならば、いつも「抱きたい」とか「欲しい」とか、ストレートに求愛してくるのだが。紫龍は、それだけのことを言うのが精いっぱいだった。
「紫龍……」
シュラは軽く絶句して、けれどすぐに立ち直って紫龍に覆いかぶさってきた。先ほど、自分が施したのとは比べ物にならないほど、熱くて深いキスが紫龍を襲う。
「紫龍、紫龍……っ」
浮かされたように紫龍を呼びながら、シュラが頬に、頤に、喉に口づけて身体をまさぐってくる。あっという間に身に着けている服の胸元が肌蹴られて、裸の胸がむき出しにされる。
「お前から誘ってくれるとは思わなかった。嬉しいよ、紫龍」
「シュラ……」
いつもより性急に、シュラが紫龍を求めてくる。
あっという間に紫龍の股間へとシュラの手が伸びてくる。シュラに慣らされている体は、深いキスをされただけで感じてしまい、そこも反応を見せ始めている。
「くぁっ!」
下着ごと服を脱がされて、直接やんわりと握られて、体が跳ねた。
のけぞって、斜め後ろにガクンと頭が倒れる。その首筋にくっきりと浮かび上がった筋肉の筋腹を、皮膚の上からシュラの舌がなぞる。筋肉の走行に沿ってシュラの舌が下りてきて、鎖骨へと付着する部分を軽く吸って、そのまま鎖骨をなぞっていく。
「ん……ぁ……っ」
内から外へとなぞっていくシュラの舌が鎖骨の中央までくると、シュラはそのまま下へとなぞる方向を変えた。シュラほどではないが、鍛えられてくっきりと浮かび上がる大胸筋を横切るように舌を這わせ、プツリと立ち上がりかけている乳頭を舐めて、口に含む。
「あっ、シュラ、シュラ……」
乳頭を舌と唇で、性器を手で。
空いた手でさらにもう一方の乳頭を。
あちこちを同時に責められて、紫龍は喘いだ。
「シュラ、あ、ダメ……そん、な……あっ!」
身悶えて、紫龍は自分の乳頭を吸うシュラの頭を両手で抱え、髪に指を差し入れた。
性急に求めてくるシュラに煽られて、紫龍も昂っていく。
シュラを求めて、全身が疼いていた。
「シュラ……シュラ、シュラぁっ」
どうしようもなく、シュラが欲しかった。
何度も名を呼んで、シュラの髪をかき乱す。
「欲しいか、紫龍?」
「あっ、あ……」
「言ってくれ、紫龍。俺が欲しいか?」
紫龍の胸から顔を上げたシュラが問いかけてくる。
太腿にシュラの性器が当たる。服越しでもわかる、はっきりとした熱を主張するシュラを感じて、頭の奥がくらくらと揺れる。
「欲しい……シュラ、あなたが欲しい」
「紫龍――っ!」
熱に浮かされたように、紫龍はただ夢中で囁いた。
はっきりと頷いた紫龍に、シュラは深く口付けた。たった今、初めて自分からシュラを求めてきた唇を奪い、欲しいと言葉を紡いだ舌を絡め取った。
紫龍の口腔を舌で愛しながら、シュラはズボンの前をくつろげて紫龍の足を抱え上げ、熱く膨れ上がった己をあてがった。
「俺も……お前が欲しい」
告げる声が、情欲に濡れているのをシュラは自覚した。
「お前が欲しくてたまらない」
ぐい、と紫龍の肉をかき分けて肉棒を突き入れていく。
いつもはじっくりほぐしてから挿入れるのだが、今はろくに前戯もしていない。紫龍を傷つけないように、一気に突き入れてしまいたい衝動を押し殺しながらシュラはゆっくりと己を埋め込んでいった。
「あ――んぅ、シュラ……、シュラ!」
ゆっくりと押し入ってくるシュラが、もどかしかった。欲しくてたまらないと言ったくせに、紫龍からも欲しいと素直に言ったのに。シュラは紫龍を焦らすようにゆっくりと押し入ってくる。
紫龍は自分からシュラを誘い入れるように腰を動かした。
「紫龍、お前……くっ」
「ああっ!」
たまらずに、シュラは一気に楔を埋め込んだ。衝撃に耐えるように、紫龍の身体が痙攣する。
「大丈夫か?」
「平気――だから、もっと……」
上体を起こして深く息をしながら問いかけてくるシュラの背中に、紫龍は両腕を回してしがみついた。
「もっと……」
その先は、継げなかった。
「紫龍――っ、く、ん……」
「あ、ああっ! あ――シュ、ラ――っ!」
シュラが激しく紫龍を突き上げてくる。先端まで引き抜いて、根元まで押し込む。何度も、何度も。
シュラの動きに応えるように、紫龍の体が揺れる。
感じる場所を抉られて、高く声を挙げる。
「紫龍、紫龍っ」
「ああっ、シュラ――あ……」
紫龍はシュラの腰に足を絡めていた。シュラも紫龍の腰を深く抱えて、ピタリと胸を合わせて激しく腰を打ちつけてくる。
速く刻む鼓動は、どちらのものかわからない程に溶け合っていた。
繋がった場所から甘い疼きが広がって、全身を満たしていく。
何も考えられなかった。
ただ、全身でシュラを感じていた。
耳元でシュラが漏らす熱い吐息が、鼓膜を揺らして耳の奥を犯していく。
シュラのTシャツが、シュラが動くたびに紫龍の胸を擦る。
そんな些細な刺激すら、身悶えするほどの快感を与えた。
「シュラ――シュラぁ……あ、あっ!」
「たまらない……紫龍、くっ、んぁ――あ……っ!」
シュラが苦しそうに呻いて、体を大きく震わせた。紫龍の中で、シュラの性器がどくんと脈打つ。
「ああ――あぁっ!」
紫龍もひときわ高い声を挙げて、欲望を解放した。
「まさか、お前から誘ってくれるとは思わなかったな」
呼吸も脈拍も落ち着いてきた頃、シュラは紫龍の髪を撫でながら囁いた。
「しかもお前、めちゃめちゃ感じてただろう?」
「……はい」
虚勢を張ったところで仕方がない。紫龍は正直に頷いた。
さっき、シュラに抱かれながらどうしようもなく感じて、あられもなく乱れたのは事実なのだから。
「本当にたまらないな、お前は」
「……?」
そんな紫龍の反応に、シュラは困ったように苦笑した。
「嬉しかった。いつも俺だけがお前を欲しがっていて、お前は仕方なく合わせてくれているんだと思っていたからな」
「そんな……! 俺だって、シュラが……その、欲しい――とは思っていましたけど、でも……」
「でも、なんだ?」
「俺が言う前に、いつもシュラが言ってくれていたから、だから言えなかっただけで……」
冷静になってみると、自分がひどく恥かしいことを言ってしまったようで、紫龍は赤面した。
「まぁ確かに、いつも俺からだったな」
真っ赤になって俯いている紫龍の顔を上げさせて、シュラは唇に軽くキスを落とした。
「でも、お前もちゃんと俺を欲しがってくれている、というわけだな」
「……嫌だったら、ちゃんとそう言っている」
「そうだな。だが俺は欲張りだからな。お前がただ俺に応えてくれるだけでは、満足できん」
拗ねたような口調になる紫龍に、シュラは少しだけ深いキスをした。
「俺が欲しい時は、ちゃんと欲しいと言ってくれ。その方が、俺は嬉しい」
「……はい」
「わかったか?」
「はい」
「だったら、お前からキスしてくれ」
求めてくるシュラに、紫龍は応えた。さっきシュラを誘ったように、初めは穏やかで軽いキスをして。次第に深くしていく。
シュラが紫龍に応えて舌を絡ませてくる。深いキスに頭の奥が痺れて、シュラに導かれるように体温が上がっていく。
唇が離れて反射的にため息をつく頃には、全身が甘く疼いていた。
「愛してる、紫龍」
「俺も……愛してます、シュラ」
素直に気持を告げて、もう一度軽く唇を触れ合わせる。
「それで?」
「え?」
「今はどうだ? 俺が欲しいか? それとも、もう満足したか?」
「あ……」
紫龍を誘うような、少し意地の悪い不敵な笑みがシュラの顔に浮かぶ。
さっきはお互いに興奮していて、勢いのままに抱き合ってしまった。それはそれで気持良かったのだが……今度は時間をかけて愛してほしい気持があった。
「まだ、欲しい……です。その、今度はもう少しゆっくり……」
「じっくり俺を感じたいか?」
「……はい」
素直に頷いた紫龍に、シュラは軽く笑った。
「俺も、もっとお前を満喫したい。愛させてくれ」
シュラの甘い囁きが耳に溶ける。
紫龍はシュラの背中に回した腕に力を込めて、小さく頷いた。
Fin
written:2008.06.09
というワケで、書いてみました。
紫龍の誘い受け(爆)
うちの山羊龍は、山羊さまが求めてきて紫龍が応える、という形が多いもので。一度書いてみたかったのです、こういうの。
まぁ単に、誘い受けな紫龍と、紫龍とアフロが絡むところが書きたかっただけ、というお話なんですが(苦笑)
このタイトル、本来は「sweet poison」でした。アコーディオニストcobaさんの中でも好きな曲なので♪ でも、このタイトルはもう一方の分室であるテニプリで書いてしまっているんですよね。
なので、今回はちょっと手を加えて、紫龍が誘い受けということで「poison」ではなく「trap」にしてみました。
ちなみに、このお話の左に飾っている写真。
実家に帰った時に、母上が煎れてくれたライチ&ローズ・ティーです。カップの中には、薔薇の花弁の砂糖漬けが入っている、という。
ちょうどこの話を書いている最中だったので、素材用に1枚撮ってしまったのでした(笑)