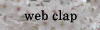牧神の午後への前奏曲
暑くけだるい夏の日の昼下がりだった。
陽光が照りつける聖域は、湿度はそれほど高くはないが、夏はかなり暑い。
そういう日には、昼寝に限る。
シュラは生まれ育ったスペインにあるシエスタの習慣を、黄金聖闘士になってからもずっと貫き通していた。その習慣を捨てたのは、聖闘士になるために修行したわずか2年ほどの間だけだ。
12人いる黄金聖闘士が守る十二宮は、それぞれが神殿のような造りになっている。が、その傍らには聖闘士が暮らすための生活スペースである奥殿がある。もっとも、奥殿といっても聖闘士に贅沢は禁物ということで、広さはせいぜい2DKほどしかないのだが。
シュラは磨羯宮にあるその奥殿で、午後の惰眠を貪っていた。
シエスタに入っているシュラを邪魔するような勇気のある者は、この聖域にはいない。
その眠りを妨げようものなら、すかさず大地を裂くほどの威力を持つ研ぎ澄まされた両手両足のうちのどれかが飛んでくるのだ。
ただ、何事にも例外というものは存在する。
この場合、その唯一の例外と言えるのがシュラの恋人であり、今やこの聖域で黄金聖闘士よりも更に上位である神聖闘士の一人に数えられている龍星座の紫龍が、それに該当する。
シエスタの習慣を持たない彼は、シュラが目を覚ます時間を見計らって磨羯宮にやってくる。そしてできるだけ物音をたてないように奥殿へ入ってきて、目覚めたシュラのためにコーヒーの豆を挽き、湯を沸かしてコーヒーを淹れる。
その日も、まどろんでいるシュラを覚醒させるコーヒー豆の香りが漂ってきた。
(紫龍か……)
恋人が自分のためだけに豆を挽き、淹れてくれる目覚めのコーヒーは何にも代え難いほど美味だ。
(そろそろ起きるか)
シュラのために風通しを少しでもよくしようと、紫龍が開けてくれたのだろう。窓から吹き込んでくる乾いた風が頬を撫でる。そんな些細なことも、とても心地が良かった。
意識ははっきりしてきたが、まだ目を開けようか…と迷っていたところへ、ふと、耳慣れない音が飛び込んできた。
風に乗ってひっそりと流れてくる、不思議な音律。
半音の微妙な音程で上下する旋律。
(これは……)
聴いたことがある、とシュラは思った。
(珍しいな、紫龍が音楽を流すとは)
目を覚ましてベッドの上に起き上がったところへ、計ったように紫龍が入ってきた。
「目が覚めましたか、シュラ?」
「ああ。豆を挽いてくれたのか?」
「ええ。今お湯を沸かしているところです。もう少し待って下さい」
自分の方が9歳年下で、年上の人間は敬わなければならない、と植えつけられているせいなのか。紫龍は恋人という関係になった今でも、シュラに対して敬語を崩さない。
敬語で話さなかったのは、初めて二人が敵同士として対峙した時だけだった、というのは何とも皮肉なことだとシュラは今でも思う。
「なぁ、紫龍? この曲はどうしたんだ?」
シュラの奥殿にはCDやMDを聴くためのコンポがある。多分それで流しているんだろう、とシュラは判断した。
「耳障りですか? だったら止めてきます」
「いや、そうじゃない」
身を翻そうとする紫龍の腕をつかんで、シュラは引き止めた。
「お前が音楽を流すとは、珍しいなと思っただけだ。この曲は確か……ドビュッシーだな。『牧神の午後への前奏曲』だ」
「はい。カミュが貸してくれたんです」
「なるほどな」
水と氷の魔術師との異名を取る、磨羯宮の隣にある・宝瓶宮を預かるアクエリアスの黄金聖闘士カミュは、フランス生まれのフランス育ちだ。フランスの作曲家を好んで聴くのは、自然なことだった。
「で、どうしてそれを流す気になったんだ?」
「カミュから聞いた時、これはあなたの曲だと思ったので」
「俺の?」
紫龍の言葉の真意がわからずに、シュラは思わず訊き返していた。
「牧神……フランス語ではファウヌと言うそうですが、これって半獣半人の神パーンのことでしょう?」
「そうだな」
「パーンって確か、ゼウスによって天空に上げられて山羊座になったんですよね?」
「神話では、そういうことになってるな」
「シュラは山羊座の聖闘士でしょう?」
問いかける形で説明されて、シュラはようやく合点がいった。
「それで、俺の曲だと思ったわけか?」
「はい」
紫龍は薄く微笑して、素直に頷いた。
その表情があまりに無邪気で、シュラは思わずからかいたくなった。
「お前……俺がテュホンに追われてナイル河に逃げ込んだものの、魚に変身し損なった間抜けな神だと言いたいわけか?」
「そういうわけじゃない!」
5人いる神聖闘士の中では優等生然としていて大人びているとはいえ、紫龍はまだ15歳の少年だ。その少年に手を出している自分もどうかと思うことは時々あるのだが……ともあれ、紫龍はシュラにからかわれてムキになった。
「俺は、ただ……」
森の牧畜の神が山羊座になっているという神話と、曲名からシュラを連想しただけなのだと紫龍は委縮したように小声で呟いた。
シュラの前でだけ見せる、歳相応の表情。そんなところも、たまらなく愛しいとシュラは思う。
「わかってる。少しからかっただけだ。気を悪くするな」
白状すると、紫龍は少し拗ねたようにしてシュラを軽く睨んでくる。
そんな紫龍に軽く笑い返して、シュラは続けた。
「それよりお前、この曲のストーリーは知ってるのか?」
「いいえ。中の解説も見てみたんですが……フランス語で書かれていたからわからなくて」
「カミュの持ち物だってんなら、そうだろうな」
聖闘士同士の会話は聖域での公用語であるギリシャ語で語られるため意思の疎通には全く不自由しないが、母国語となると話は別だ。紫龍はもともと日本語で、修行地として赴いた先の中国語もわかる。シュラはスペイン語と、教養の範囲で英語とフランス語も日常会話には不自由しない程度に理解できる。
「ストーリーがあるんですか? この曲に」
「ああ」
フランスの作曲家、クロード・ドビュッシーが生んだこの『牧神の午後への前奏曲』は、彼と同時代を生きたフランスの詩人ステファン・マラルメが作った詩『牧神の午後』を元に作られている。
「簡単に話すと、こうだ」
シュラは流麗なフルートの旋律に乗せるように、ストーリーを簡単に説明してやった。
夏の暑い日の昼下がり、牧神が休んでいるところに美しい妖精や水の精たちが現れ、やがて牧神はその妖精たちに欲情する。しかし、ひとあたり戯れるとやがてそれにも飽きてしまい、牧神は自然界を手中に収める夢を見てまどろむ。
「ま、神といっても半獣半人、下半身は獣だからな。完全に人型の神よりも本能に忠実なんだろうぜ」
曲は、ちょうど一番の盛り上がりを見せる部分にさしかかっていた。
牧神が妖精や愛の女神ヴィーナスを思い浮かべて欲情し、戯れるシーンが音によって表現されているところだった。
言いながら、掴んだままだった紫龍の腕を強く引いて、ベッドに引きずり込む。紫龍は抗わなかった。
東洋人の特徴なのか、紫龍はもともと体臭が濃い方ではない。けれど暑さのせいで滲む汗が、体臭と混ざって日頃よりほんの少しだけ強く紫龍の香りを浮き立たせている。
首筋に鼻を擦りよせて、シュラはその香りを楽しんだ。
「ちょっと、シュラ……」
紫龍がわずかに身をよじる。男二人で抱き合うには少々狭いベッドの上で逃れようとしても、それは叶わない。シュラはしっかりと紫龍を抱き寄せた。
「俺が牧神パーンだと言うなら、その俺を欲情させるお前はさながら水の妖精ってトコだな、紫龍」
暑気を帯びてしっとりと汗に濡れる体を、服の上からそっと撫でる。下になっているシュラにもサラリとかかってくる紫龍の長い黒髪をかき上げて軽くキスをすると、少し拗ねたような声で反論された。
「俺はそんなかわいらしい存在じゃありませんよ」
「知ってる。お前は廬山の大瀑布を逆流させる龍の化身だろう?」
もちろん、シュラもその姿を目の当たりにしている。底知れぬ小宇宙に怖れを抱いたこともある。
「だが、今こうして俺に抱かれてるお前は、水の妖精よりも美しくて愛らしいと思うんだがな?」
「……かわかわないで下さい」
「からかうとは心外だな。本音だ」
さらに拗ねてしまったような声になる紫龍に、さっきよりも少し深くて長いキスをする。
「……っ」
「ちょうど曲もクライマックスだ。官能の嵐、ってトコだな。俺たちもどうだ、紫龍?」
自分でもよくこんな声音が出せるものだ、と常々感心せずにはいられない、紫龍専用の甘い声で囁く。
「こんな、昼間から……」
外はまだ、太陽が燦々と大地を照らしている。
その上、紫龍は風通しを良くするためにさっき奥殿の窓を開けたのだ。その状態でコトに及べば、最悪外に声が漏れて中で何をしているのか、通りかかった者にはたちどころにバレてしまう。……もっとも、二人の関係はとっくの昔に聖域で知らない者はいないほどに知れ渡っているのだが。
「それに……」
「それに、何だ?」
「あなたがパーンで、俺が水の精だというのなら。あなたにとっては俺はひと時の戯れで、すぐに飽きてしまうんでしょう?」
「俺は確かに山羊座の聖闘士だが、半分獣で頭の弱いパーンとは違う。お前だって、水の妖精なんてかわいい存在じゃないんだろう? だったら、俺たちが曲のストーリーに沿ってやる必要はないと思うんだがな?」
言いながら、シュラは紫龍を自分の下に組み敷いた。
唇を重ね合わせて、軽く舌を出して口裂をつつく。自分の舌を迎え入れるようにと誘うと、紫龍は恥じらうように軽くシュラを押し返しながらも、ゆっくりと口を開いた。
「ん……っ」
紫龍の舌を探り当ててぞろりと舐めると、紫龍は鼻に抜けるような甘い吐息を洩らす。
それが更にシュラを煽った。
キスをもっと深くして、服の上から紫龍の胸を探ろうと手を伸ばした時。
シューーーーッ!
ふわふわととらえどころのない、けれど色彩豊かで幻想的な音楽と、二人の甘い吐息が織りなすハーモニーをぶち壊す無粋が音が、キッチンから響いてきた。
「あ、お湯がっ!」
あともう一歩で夢見ごこちに蕩ける表情になるところだった紫龍が、その一瞬で我に返った。
「お湯が沸いたみたいですね。コーヒー、淹れてきます」
まだ日の高い真昼間から事に及ぼうとした気恥ずかしさからなのか。紫龍は口早にそう言って、気が抜けてしまったシュラの腕からそそくさと抜け出した。
パタパタとキッチンへと急いでいく。
(あと一歩ってところだったんだがな)
紫龍を抱きそこなってしまったシュラを、再び夏の暑気と、わずかな倦怠感が襲う。
唇や腕にはまだ紫龍の感触が残っている。
ベッドにも、紫龍の温もりがある。
軽く目を閉じただけで、紫龍の匂いまで思いだすことができる。
(これじゃ、本当にパーンだな)
紫龍には話さなかったが、『牧神の午後』は実際はもっと長い夢想詩だ。牧神パーンは妖精を抱く夢を見て、さらに空想を広げて愛の女神ヴィーナスにまでたどり着く。けれど、どれほど夢想してもあくまでも幻想の中で起きた出来事でしかない。本当に腕に抱いて、愛を交わしたわけではないのだ。
(紫龍のヤツ……)
シュラの曲とは、なかなか言いえて妙だ。この状況では、特に。
夢の中で妖精やヴィーナスと戯れた牧神パーンは、再び静寂の中で眠りに落ちていく。
官能的な響きを帯びたフルートの静かな旋律が、風に乗って聞こえてくる。
その旋律に導かれるように。
シュラは再び重くなってきた目蓋を閉じた。
Fin
written:2008.4.3
曲のタイトルから思いついた短編です。
シュラさん=山羊座の聖闘士。
山羊座になっている神=牧神パーン。
ということで、紫龍さんがシュラさんを「パーンだ」と言うのなら、シュラさんは紫龍さんを「水の妖精だ」と返してみたらどうだろう?と。
ちなみに、どうしてこの曲に思い至ったかと言いますと。
三次元のダーリン、指揮者・金聖響さんの2008年のコンサート・シリーズが「音楽至上主義」というものでして。4月の第1回目、プログラムの最初に演奏されるのがこの曲だからなんですね(笑)