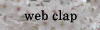甘ったれクリーチャー
夢の向こうから、愛しい声が呼んでいる。
とシオンは思った。
「これ、シオン」
声に導かれるように、浅くなっていた眠りから急激に浮上する。
「起きぬか。もう朝じゃぞ」
うっすらと目を開けると、愛しい人の顔があった。少し怒ったような表情で、シオンに呼びかけている。
「シオン」
「んー、童虎?」
前に木の留め具がついた詰襟の、ゆったりとした服に身を包んだ童虎が、身を乗り出すようにしてシオンを見ていた。
「んー、童虎? ではないわ。とっとと起きぬか」
ぶっきらぼうな口調だが、言葉の裏にはシオンへの愛情が溢れている。
……と、シオンは勝手に思っている。
そもそも、童虎は朝が早い。
彼の修行地であり、任務がない時はいつも隠遁生活を送るかのようにして暮らしていた中国・廬山五老峰では、日の出とともに起きて日没とともに寝る、という昔ながらの健康的な生活を送っていた男だ。生活の場を聖域に移してもなお、童虎の生活スタイルは変わらない。流れゆく自然に身を任せ、逆らわない。
一方のシオンはと言えば。
お世辞にも寝起きがいい、とはとても言えないほど寝汚い。教皇としてこの聖域に一人で君臨していた時は、かなり自分を律していたのだが。ハーデスとの聖戦を終え、童虎と共に復活して再び教皇に返り咲き、童虎と共に暮らすようになってからはすっかり元に戻ってしまっている。
……つまり、朝はパキッと起きるよりも惰眠を貪っていたい、という性質なのである。
「もう少し寝かせろ」
「ダメじゃ。もうとっくに日は昇っておる」
「……」
哀願しても、童虎はバッサリとシオンを切り捨ててくれる。
面白くない、と思った。
仮にも、243年越しの恋をようやく実らせ、まだ蜜月真っ最中と言っていい時期なのだ。せっかく恋人になったのだから、もう少し甘い朝を味わわせてくれてもよいではないか。
シオンはそう思った。
(たまには甘えてみるか)
「いつまで寝ておるつもりじゃ?」
「……おはようのキス」
呆れたように問いかけてくる童虎に、シオンはとびっきり甘えた声で囁いた。
「なっ……」
シオンの口から飛び出てきた言葉に、童虎は顔を真っ赤にして絶句する。
「お前がキスしてくれれば、起きてやらぬでもないぞ」
「ふ、ふざけたことを言うでない!」
さらに畳みかけてやると、恫喝が降ってきた。
「朝っぱらから何という不埒なことを考えておるのじゃ、お前は!」
「不埒も何も、恋人に甘えたいと思うのは自然な欲求であろう?」
上目使いで見上げると、童虎は呆れたように言い返してきた。
「いい年をして子供のようなことを言うでない!」
そして童虎は実力行使に出た。
つまり、シオンの上掛けを剥ぎにかかったのである。
「何をする、童虎!?」
「お前がごねるからじゃ」
上掛けを剥ごうとする童虎と、死守しようとするシオンがベッドの上で軽くもみ合う。
「観念せい、シオン!」
「キスくらいでそんなにムキにならずともよかろう、童虎!」
子供のような言い合いをしている間に、童虎がベッドへ乗り上げてくる。
シオンは上掛けをぐるりと体に巻きつけて、剥ぎ取ろうとする童虎から死守した。
「……強情なヤツじゃ」
「お前がキスしてくれれば起きる、と私は初めから言っておる」
「まだ言うか?」
「キスをするのも、セックスに誘うのも、いつも私からだ。たまにはお前からキスしてほしい、と思うのがそんなに悪いか?」
「それは……」
寂しそうに沈んだ声を出すシオンに、何としても起さなければならない、という童虎の決意が揺らぐ。目を少し潤ませて、上目使いで見つめてくるシオンの表情を見ていると、自分が無体を働いているような気分にさせられた。
自分と同じだけ年を重ねているというのに――シオンには13年間死んでいた期間があるのだが――シオンは子供のように駄々をこねる。もっともそれは童虎を前にしている時だけで、部下である黄金聖闘士や教皇に仕えている侍女たちの前では毅然とした態度を見せている。
「わしがお前に接吻してやれば、起きるのだな?」
「ああ、起きてやる」
問いかけに答えて、シオンは目を閉じて童虎のキスを待った。
「………!」
童虎はしばらく逡巡して、ようやく覚悟を決めたかのように、がっしりと掌でシオンの両頬を包んだ。そしてギュッと固く眼を閉じて、キュッと引き結んだ唇をシオンのそれに押し当てる。そのままきっちり3つ数えて、童虎は唇を離した。
「し、してやったぞ。早く起きるのじゃ」
よほど恥ずかしかったのだろう、耳まで真っ赤になって早口になる童虎に、シオンは少し呆れたように問いかけた。
「……童虎、お前は私をからかっているのか?」
「何がじゃ?」
「こんなもの、挨拶程度にしかならぬ。キスとは認められんな」
「な、何じゃと!?」
童虎の性格を考えれば、唇を押し当てただけで精一杯だったのだろう、とシオンにはわかっていた。だが、今朝はそれだけでは足りない。甘えたいモードは最大レベルに達している。
「わからぬなら教えてやる。キスとは、こういうものを言うのだ、童虎」
言葉でわからないなら、体で教え込むしかない。
シオンは童虎の後頭部に手を回し、ぐいと引き寄せて深く唇を重ねた。
「んっ! んー……ぅ、――……っ!」
唇を重ね合わせて、たちまちのうちにシオンの舌が童虎の口腔を犯しにかかる。歯列の裏側をなぞり、口蓋を舐め、舌先で頬の内側をくすぐって、舌を絡め合わせる。
「んぅ……っ」
角度を変えて深く口づけた頃には、童虎は鼻に抜けるような甘い吐息を漏らしていた。そしてシオンの背中に、後頭部に童虎の腕が回されて、自分からもシオンを求めるようになっていた。
「童虎……かわいいな、お前は」
耳元で甘く囁いて、シオンは体勢を入れ替えた。自分の上に乗り上げていた童虎を、体の下に組み敷く。
耳朶を甘噛みして、耳の後ろに音をたてるキスを繰り返して、服の上から胸を弄る。ぷつりとその存在を主張する突起を服の上から探って軽く擦ると、童虎の口から嬌声が漏れた。
「あっ……ダメ、じゃ……――ん、シオン……っ」
きゅ、と軽く突起を抓まれる刺激に、童虎はピクリと体を震わせた。
浅い息を吐いて、眉を寄せて感じる表情を見せる童虎の顔が、カーテンから漏れる朝日に照らされてはっきりと見える。
「何がダメなのだ? この程度で、もうそんなに感じているクセに」
「言うでないっ……ぁ――……んっ!」
手早く留め具を外したシオンに、直に触れられて。ビクッと童虎の体が跳ねる。
「シオン、やめ……っ」
「やめぬ。お前があんまりかわいいんでな、もうこんなになっておる」
サクサクと童虎の服を脱がせながら、シオンはこれ見よがしに童虎の股間に自分の熱を擦りつけた。
「あっ!」
じわじわと責められて煽られていた状態で、いきなり直接的な刺激を加えられて。童虎はたまらない様子で身を捩った。
戯れのような愛撫を受けていた体は、熱と質量をもったシオンの牡を感じて一気に火がついた。熱が集まり始めていたそこが、急激にシオンと同じ熱と硬さを帯びる。
「お前も、その気になっておるであろう? 鎮めてくれるな、童虎?」
「こんな、朝っぱらから……不埒な男めっ!」
情欲に潤む眼で睨みつけてくる童虎に、シオンはふっと余裕の微笑を浮かべて見せた。
「私もお前も、18歳の肉体を持っているのだ。朝が最も元気なのは、お互い様だろう?」
誘うように問いかけながら、唇に音をたてて軽くキスを落とす。
「それに……その不埒な男にこんなにされるのが好きなのだろう、お前は?」
言いながら、シオンは童虎の下穿きを下着ごとはぎとって、硬くそそり立っている童虎の熱に自分のそれを擦り合わせた。腰を動かして擦りつけながら、ゆったりとした夜着を脱いで、裸の胸を合わせる。
「あ、あ……っ、シオンッ!」
いつも童虎の中で暴れているシオンの楔が、自分のそれにピタリと重ね合わされている感触に、眩暈がしそうになる。
二人の陰茎を一緒に擦るシオンの手の動きに、童虎は溺れていった。
シオンを起しに来た理由も、外はもう日が昇っていて、室内も明るくなっていることも。
そろそろ弟子の紫龍や、シオンの補佐についているサガがやってくる時間だということも。
全て忘れて、シオンの愛撫に翻弄される。
「あっ……んぁ――……っ!」
童虎はすがりついたシオンの肩に、思わず爪を立てていた。皮膚に爪が食い込む感触に、シオンは童虎の昂りを感じていた。
「欲しいか、童虎?」
「欲し、い……シオン――……あっ!」
先端の窪みを強く抉られて、ビクンと童虎の体が跳ねる。
二人分の先走り液に濡れる指先をペロリと舐めて、シオンは童虎を促した。
「ならば、足を開け、童虎」
「あ……んっ」
童虎は憎まれ口を叩くことも忘れて、シオンに促されるまま、素直に足を開いてシオンを迎え入れようとした。茂みの中に屹立する童虎の牡は、シオンと童虎の先走り液で濡れそぼっている。それが幹を伝い落ちて、会陰の奥にある秘所まで濡らしている様子が全て、シオンの眼前に曝される。
日頃の童虎からは想像もできない淫らな様子に、シオンの牡としての本能がどうしようもなく駆り立てられる。
「人をさんざん不埒な男だと罵っておいて、こんなに乱れて私を誘うお前はどうなんだ、童虎?」
意地悪く囁いて、シオンは童虎の望むものを与えてやる。
ぐい、と押し入ると童虎は甘い声を上げて、シオンを迎え入れた。
「あ、ん……っ、あ……――っ!」
強烈な圧迫感が童虎を襲う。
押し入るや否や、自分に絡みついてくる童虎に、シオンは眩暈がしそうなほどの快感を覚えていた。
「動くぞ、童虎」
「あ……あっ!」
衝動のままに、シオンは童虎を突き上げた。
「おはようございます、サガ」
教皇の間へやってきた紫龍は、執務室にサガが一人でいることを訝しみながらも、礼儀正しく朝のご挨拶をした。
「おはよう、龍星座」
「今朝はお一人なんですか? シオン様は……」
「まだ表には出てこられていない」
「そうなんですか」
尋ねると、サガは少し複雑な表情をして答えてくれた。
「それで、君は何をしに来たのだ?」
「朝稽古の時間になっても老師が下りて来られないので、お迎えに来たんです」
「なるほどな。老師もまだ寝殿の方にいらっしゃるようだな」
「もしや、体調でも崩されたのでしょうか?」
とっさに思いついた疑問を口にした紫龍に、サガはますます複雑そうな表情を見せた。
「そういうわけではないと思うが……」
「俺、ちょっと様子を見てきます」
「待て、龍星座!」
執務室の奥にある寝殿へ向かおうとした紫龍を、慌ててサガが止めた。
「サガ?」
「いや……奥へは行かない方がいいと思うぞ」
「え? どうして……」
理由を尋ねようとした紫龍の耳に、明らかにそれとわかる嬌声が聞こえてきた。
「あ……あっ、も…っと……――んっ、もっとじゃ、シオン!」
「童虎……あ、くっ!」
いつもは柔らかく深みのある童虎の声が、高く上ずっている。呼応するシオンの声も、切羽詰まったような響きを帯びていた。
「……わかったか?」
問いかけられて、その意味がわからない紫龍ではなかった。
「シオン様も老師も、お取り込み中のようだからな。しばらくは表に出て来られまい」
「そのようですね……」
そして、サガが何とも複雑な表情をしている理由も悟った。
「磨羯宮に戻って、稽古はシュラにつけてもらうようにします」
「その方が賢明だな」
頷くサガに、紫龍は問いかけた。
「サガはどうなさるんですか?」
「シオン様が満足して表に出てこられるまで、私にできる仕事を終わらせておくしかないだろうな」
「そう、ですよね……」
冷静さを装って答えてきたサガに、紫龍は心から同情した。
「お邪魔してすみませんでした。失礼します」
紫龍は深々と頭を下げて、教皇の間を辞した。
「あっ……ああっ! シオン、シオンッ!」
師である童虎の嬌声に送られながら。
Fin
written:2008.09.11
え~、何のヤマもオチもイミもないお話で申し訳ない(汗)
エル龍を書き始めるより少し前に、某笑顔動画でとあるミニドラマを十数年ぶりに聞きまして。
そのミニドラマってのが、飛田×鈴置(まぁ、ぶっちゃけ健×小次?/爆)でして。
その中で、飛田さん演じる後輩が、鈴置さん演じる先輩に向かって、飛びっきり甘い声で強請るんですよね。
「おはようのキス」
……さすがに、シオン×紫龍だとちと支障があるので(笑)
お師匠さんにやっていただくことにしました(^^)
ちなみに、タイトル名はスピッツのアルバムからいただきました。
ちょっとHな歌詞で、大好きな1曲です♪