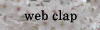恋のはじまり
それは 恋のはじまり
体にのし掛かる重みで、童虎は眠りの淵から呼び覚まされた。
黄金聖闘士の地位は弟子に譲って引退したとはいえ、童虎は教皇補佐の参謀であり、女神の聖闘士だ。その童虎が何者かの侵入を許し、あまつさえ寝台に乗り上げてくるまで眠り込んでいて気づかなかったという事実に、愕然とした。
相手は小宇宙も気配も完全に断って行動していた。
「童虎、童虎……」
何者だ?と考えるよりも先に、呼びかけられた声で気がついた。二百数十年前に起きた聖戦を共に生き抜き、二度目の聖戦を迎えて再会し、今は再び無二の親友として共に歩んでいる男。次の教皇が決まるまで、つなぎとして再び教皇の座に就いている元牡羊座のシオンだった。
「童虎……」
思いの詰まったような声で童虎を呼び、シオンは童虎の頬に軽く触れてきた。癖のあるシオンの長い髪が、童虎の顔の横にバサリと落ちてきた。
教皇職の傍ら、数少ない聖衣の修復師としての仕事もこなしているというのに、シオンの指は滑らかで柔らかい。程良い温もりを持った指が、掌が、童虎の頬を包んだ。
(何故、シオンが……?)
考えようとして、次の瞬間。童虎の思考は停止した。
(っ!?)
唇に息がかかったと思ったら、何か柔らかいもので塞がれていた。口づけられたのだ、とわからない童虎ではない。何故だ!?と思うより先に、闇に溶けるように密やかな声で、シオンが囁いた。
「愛している、童虎……」
もう一度、今度は先ほどよりも少し長く口づけられる。その間に、シオンの長く細く、柔らかい指が童虎の首筋や胸元を服の上からまさぐる。
童虎を起こさないように気を遣いながらも、触れずにはいられない。起こしても構わないから、口づけを深くして、愛撫の手を強めたい。だが、もし起こしてしまったらどうする?
逡巡するシオンの気持ちが、童虎にも伝わってきた。息がかかるほどの距離では、どれほど小宇宙を断って気配を殺しても、覚醒した童虎には気持ちが伝わってきてしまうのだ。その想いが強いだけに、なおさら。
しかし、心の中で呼びかけてしまったら、童虎が起きているとシオンに伝わってしまう。それだけはさすがにお互いに気まずい、と童虎はとっさに判断した。
「……ぅ、ん……」
唇が離れた隙に、眠りが浅くなってふと息をついたと見せかけて、童虎は深く息を吐いて軽く身じろぎをした。
「――っ!?」
はっと我に返ったシオンが、息をのんだ。慌てて童虎から離れ、寝台から下りて、猛スピードで童虎の寝室から出ていった。
(なんだったのじゃ、今のは……!?)
童虎は目を見開いて、シオンが去っていったドアへと顔を向けて凝視した。
頭に血が上って、完全に目が冴えた。鼓動がいつもよりもずっと早く、強くなって、全身でバクバクと脈打っているのがわかる。
唇の柔らかさや指の温もりが、触れられた場所に残っている。
(何故、シオンが……!?)
寝台の上で寝返りを打っても、答えが出るわけもない。
目の前から去った相手のことで頭が埋め尽くされて。童虎は再び眠りへと落ちることもなく、答えの返ってこない問いを何度も頭の中で繰り返した。
翌朝、童虎は完全に寝不足状態で執務室に出仕した。
正直なところ、シオンとどんな顔をして会えばよいのか、童虎は迷っていた。だが、シオンは童虎が気づいていたことを知らない。普通の顔をして会えばいいのだと頭ではわかっていたが、どうやって普通の顔をすればいいのか、それがわからなくなっていた。
童虎が執務室に入って業務を始めてから、少ししてシオンが出てくる。
「おはよう、童虎」
「お、おはよう……」
案の定、シオンはいつも通りに声をかけてきた。昨夜のあれは聞き間違いだったのか、と思うほどに。
書類に目を通している振りをして、目線だけを上に向けてシオンの様子を伺う。
「どうした、今朝は元気がないようだな。寝冷えでもしたか?」
しかし、こういう所だけは、シオンはやけに勘がいい。聖衣の声を聞くことができる所以なのか、いつもと少し違う様子を見せただけで、シオンはそれを気にかけてくれる。昨日まではただ気配りが上手いとか、気が利いているとか。その程度にしか思っていなかった。だが、昨夜。あんなことがあって、一夜明けてから同じことをされると。何か特別な想いがあるためなのか、と童虎は勘ぐってしまっていた。
「童虎?」
「……いや、な、何でもない。別にわしは何もないぞ」
「……そうか? ならば良いのだがな」
答えない童虎を訝んで、シオンが近づいて顔をのぞき込もうとしてくる。それを童虎は寸前で止めた。
「沙織お嬢様への拝謁は済んだのか?」
できるだけ平素と変わらないようにと努めながら、童虎は話を逸らした。
「ああ。今日は天馬星座やお前の弟子を連れて、聖域の外へ出てくるらしい」
シオンは答えながら童虎から離れ、自分の執務机についた。
「そうか。紫龍と星矢がおるのならば、安心じゃの」
「お前の弟子は苦労するだろうがな」
「そうじゃの。沙織お嬢様の護衛以外の仕事が増えそうじゃからのぉ」
「二人分のお守りをすることになるだろうからな。もっとも、お前の弟子はそれ苦労とも思わぬのであろうが」
「あやつはもともとそういう男じゃ」
「また弟子自慢か? それくらいにして、仕事に励め」
「おお、言われずともそうするわい」
シオンが言葉を切って自分の仕事に入るのを見て、童虎はそっと心の中で安堵のため息をついた。
昼食後、自由な時間を得た童虎は教皇の間を出て、今は弟子の紫龍が預かっている天秤宮へ下りた。
「紫龍、入るぞ」
宮の壁の一角にある、両開きの重々しい扉を開けて、生活スペースである寝殿へと入っていく。もともと自分が預かっていた宮とはいえ、今ここの主は童虎ではない。一応声をかけて、童虎は奥へと進んだ。
「紫龍? おらぬのか?」
声をかけて中に入っても、弟子からの返事はない。律儀を絵に描いたような性格をしている弟子には珍しい、と怪訝に思ってリビングルームに入った時、童虎はようやく思い出した。
(そういえば……)
今朝、アテナに拝謁したシオンが話していたことを。紫龍は今日、アテナのお供でアテネ市内にあるグラード財団の支社へ出向いているのだ。
(留守じゃと言っておったな)
そんなことも思い出せないほど、尋常ではないほどに冷静さを欠いている自分がおかしくなる。午後になっても、まだ昨夜の事で動揺している。
「わしとしたことが……」
引き返そうとして、ふとリビングルームのテーブルの上に出しっぱなしになっている雑誌が目に止まった。きっちり片づける紫龍が雑誌を出しっぱなしにするとも思えない童虎は、恐らく天馬星座の星矢やアンドロメダ座の瞬あたりが散らかしたのだろう、と推測していた。
紫龍と行動を共にしている青銅聖闘士たちが、アテナである沙織のために買ってきた物をここに持ち込んで、読んでいたのだろう。その雑誌の表紙に書かれている文字が、童虎の気を引いた。
「恋する星座占い……?」
日頃の童虎ならば、黄道12星座を守護に持つ聖闘士である自分が星占いなど……と一笑に伏すところなのだが。その日の童虎は、それを無視することができなかった。
雑誌を手にとって、件の特集が組まれたページをめくる。
その雑誌に掲載されていた星占いは、単に12星座の運勢を書いているだけのものではなかった。1星座を更に3つに分け、期間の前3分の1に生まれた者、中3分の1に生まれた者、後3分の1に生まれた者……とより細かく運勢がわかるようになっていた。
童虎が生まれたのは、10月20日。天秤座の中でも終わり頃になる。その運勢が書かれたページを目で追って、童虎は思わず固まった。
「なんじゃ、これは……!?」
書かれている文字を、童虎は思わず頭の中で反芻した。
この期間に生まれたあなたは、恋愛運が絶好調。思いがけない人から告白されることも。友人から恋人へと進展する絶好のチャンスです。特に牡羊座の相手との恋が急激に進展します。
「牡羊座……シオンではないか?」
ことごとく的中している内容に愕然とする。童虎にとって友人であり、思いがけない相手でもあり、牡羊座の聖闘士であったシオンからの告白。そんな素振りなど一度も見せたことのなかったシオンが急に見せた想い。書かれている通り、昨夜突然、シオンは童虎との距離を詰めてきた。
教皇の務めとして毎夜星見をするシオンは、星座の動きを肉眼だけでなく小宇宙の流れでも読みとる。雑誌に書かれている星占いなど、比べ物にならない精度で。
「それで、昨夜だったのか?」
シオンならば、童虎を手に入れるためにもっとも星の配列が良い日時を読み説くことも不可能ではない。急に行動を起こしたシオンのことを、童虎はそう解釈した。
(じゃが、いつから……何故わしなのじゃ?)
シオンに直接問いかけない限り、わかるはずのない問いを頭の中で繰り返す。目の前にいない相手のことで、頭の中がいっぱいになっている。昨夜のことを思い出すと、また心拍数や体温が上がってくる。
「紫龍もおらぬようじゃし、ここにいても仕方がないの」
童虎は天秤宮を出た。
とはいえ、自由に行動できる休憩時間はまだ余裕がある。このまま教皇の間に戻って、シオンと顔を合わせるのは何故だか気が引けてしまう。
「そうじゃ……」
ふいに、脳裏に一人の少年の顔が浮かんだ。
二百数十年前、一途に童虎を愛し、思いの丈をぶつけてきた少年。心がそのまま表れたような、真っ直ぐな目で自分を見つめてきた少年。恋愛とは無縁だった童虎の、最初の恋人となった少年。
二百数十年前の聖戦で冥王ハーデスの依代となった親友を救うために必死で戦い、命を落とした彼が眠る墓地へと、童虎は足を向けた。
聖域の東の外れにある、アテナ神殿を望むことのできる鎮魂の丘。その丘の下には墓地が広がっている。神話の時代から幾度となく続いてきた聖戦や、任務の最中に命を落とした聖闘士たちが眠る墓地。
だが、墓標の下に遺体が埋まっていない者も多い。空を裂き、蹴りで大地を割り、常人ではありえない力を持って戦う聖闘士は、凄絶な最期を迎える者が多い。一片の肉も残らず消滅する者もいれば、戦場が崩れて遺体が見つからない者もいる。
墓標に刻まれるのは、聖闘士の守護星座と、青銅・白銀・黄金の区別と名前のみ。
童虎が急に墓参りを思い立った相手は、その名をテンマという。テンマは冥王ハーデスに従う冥闘士を追っていて、偶然見つけた少年だった。冥王ハーデスの依代である少年と、人として生まれた先代のアテナと共に孤児院で暮らしていた彼は、修行をしたわけでもないのに小宇宙に目覚めていた。そして神話の時代からアテナの側に侍り、ハーデスが宿敵と狙う天馬星座の宿命を負っていた。
正式に聖闘士とするべく聖域へと連れ帰り、弟子ではなく弟分として稽古をつけた少年。その彼が自分を見つめる視線が単なる兄貴分ではなく、別の感情を持っているのだと気づいたのは、今回のシオンと同様、彼に突然キスをされた時のことだった。
『俺はアンタが好きなんだ。アンタは俺のこと単なる弟分としか思ってないかもしれないけど、俺は違う。アンタよりももっと強くなって、アンタを守りたい』
遠い昔の思い出ではあるが、今でもまだ彼のことはよく覚えている。紫龍のように弟子としてではなく、もっと親しみがある弟分にしたのは、童虎自身も彼に対して何か思うところがあったのだろう。そう気づいたのは、テンマの想いを自然に受け入れて恋人という関係になってからのことだった。
二百数十年の間五老峰を離れられなかった童虎は、聖戦が終わって聖域で暮らすようになって、最初にテンマの墓を訪れた。以来、任務に忙殺されてなかなかここには来られなかった。
(冷たい、と言ってお前は拗ねるかの)
恋人になってからもテンマが年下であることに変わりはなく、幼な子のように拗ねていた彼の顔を思い出して、童虎はつい口元を綻ばせた。緩みかけた表情と気持ちが、視線の先に見つけた後ろ姿に再び固まった。
「シオン……」
そこには先客がいた。
遠目から見ても間違えようのない、癖の強い長い髪。聖域で唯一、教皇だけが身につける紫紺の法衣。昨夜童虎の寝床に忍んできたシオンが、テンマの墓の前にいた。
「……、テンマ」
テンマを弟分としてかわいがっていた童虎の親友だったこともあって、シオンもテンマとはそれなりに縁が深い。
(いったい何を?)
呟くような声でテンマの墓標に向かって話しかけるシオンの声は、聞き取ることができない。童虎は小宇宙と気配を殺して、少し近づいた。
「いつも童虎に抱きついたりキスをしたりするお前を見ていて、微笑ましいと思いながらも私は童虎に対してそういう気持ちになることはない、と思っていたのだがな。時が経てば、人の心というものは変わるらしい」
シオンの話を盗み聞きながら、童虎は思い返していた。テンマはいつも童虎に触れたがった。人目をはばからず……ということはさすがになかったが、二人きりになるといつも抱きついたり、キスをしたり……と童虎に触れてきた。無二の親友であったシオンにそれを見られたことは、一度や二度ではなかった。
「今ならば、お前の気持ちがわかる。昨夜童虎に触れてみて、はっきりとわかった。私は童虎を愛している。恐らくは、お前がかつて童虎を愛していた以上にな」
シオンははっきりとそう告げた。童虎のかつての恋人に向かって。
「お前と童虎が恋人同士であったのは、もう二百五十年近くも前のことだ。こうして再び生を受けて若い肉体を得た今、童虎も思い出に浸り続けるわけにもいくまい。テンマよ、童虎は私が貰うぞ」
シオンの告白に、嬉しさと気恥ずかしさが入り交じった思いがこみ上げてきた。昨夜シオンの指が触れた胸元が、熱く甘く疼く。自分よりもずっと背が高くて、細い指に似合わぬほどがっしりとした体つきをしているシオンに触れたい、と。
童虎は小宇宙も気配も断ったまま、衝動のままに動いた。
「シオン」
「童、虎……?」
背中越しに抱きついて呼びかけると、戸惑いを隠せない声が童虎を呼んだ。
「貰うなどと、人を犬や猫のように言うでないわ、このバカ羊」
「私がバカ羊ならば、お前は虎猫だ。貰う貰わぬの話をしたところで、問題はなかろう」
照れくささも手伝って憎まれ口を叩くと、笑いながらしれっと言い返された。
「誰が虎猫じゃっ!」
「猫のような気まぐれさで私を惑わせ、猫のような愛らしさで私を魅了するからな、お前は。加えて、猛虎の牙と爪を隠し持っているが故の美しさも持ち合わせているのが、たまらない」
少し興奮気味に大声を出した童虎の腕が緩むと、シオンは童虎を振り返って微笑しながらそう続けた。柔らかく緩んだ目元と口元が目に入り、童虎を見つめる温かい眼差しを向けられて、童虎はいっそう落ち着かない気持ちになる。
思わず目を逸らして、童虎はついムキになって食ってかかった。
「……誰がそのようなことを申せと言うたのじゃっ!」
「お前が私をバカ呼ばわりするからだ。それで、どこから聞いていたのだ?」
「……何がじゃ」
「盗み聞きしていたのだろう? どこから聞いた?」
シラを切ろうとしたのだが、察しのいいシオンに阻まれた。ここはおとなしく白状するしかない、と腹を括って童虎は話した。
「わしに触れたがっていたテンマの気持ちがわかるとか何とか、お前がほざいておった辺りからじゃ」
「そうか」
「だいたい、何なのじゃ、お前は。わしを好いておるならば、テンマに言う前にわしに直接言うのが筋であろうが。それを、いきなり夜這いなどという手段に出た挙げ句、間接的に想いを告げられるなどありえぬわ」
話しているうちに、昨日から童虎の身に起きたことがようやく童虎の頭の中でも整理できてきた。
「怒っておるのか?」
「当たり前じゃ。寝込みを襲われて怒らぬ者などおるのか?」
「気づいていたのか。今朝お前の様子がおかしかったのは、そのせいか」
「う……それは、じゃな……」
シオンに言い当てられて、童虎は思わず言葉に詰まる。
「本気で怒っているならば、私は今頃打撲どころでは済まぬ状態にされているであろうよ。寝込みを襲ったことは謝るが、お前もまんざらではなかったのだろう?」
「勝手に解釈するでないわ、バカ羊めっ」
微笑を含んだ声でしれっと図星を突かれて、童虎は反射的に憎まれ口を叩いた。それも肯定の印と受け取ったのか、シオンが童虎の頬に触れてきた。童虎よりも大きなシオンの掌が童虎の頬を包み、指先でくすぐるように童虎の頬や耳の後ろを軽く撫でてくる。
「済まない、童虎。私も自分自身の気持ちに戸惑い、持て余しているのだ。正直、ここまでお前を愛しいと思うようになるなど、想像もしていなかった」
宥めるようなシオンの手つきに、ささくれたようになっていた童虎の気持ちも落ち着いてくる。
「愛している、童虎」
シオンの顔が近づいてきた。と思うと、唇の端に軽いキスを落とされた。軽く触れるだけのキスをして、角度を変えて口づけてくる。
「……」
童虎は目を閉じて、シオンの口づけを受けた。
抱き締めてくるシオンを抱き返すと、シオンは強く唇を重ねて童虎の口腔へと舌を潜り込ませてきた。更に服の上から明らかに愛撫する手つきで体を撫でてくる。
「ちょ……っと、待つのじゃ、シオン」
「何だ、童虎? 不都合でもあるか?」
「ある。ここでは、その……」
ここは童虎やシオンの同胞たちが眠る墓所。加えて今二人がいるのは、かつて童虎の恋人であった天馬星座のテンマの墓石の前だ。
童虎が言わんとしていることをすぐに察して、シオンは口の端を歪めて不敵な微笑を浮かべた。
「なるほどな、見せつけられてはテンマが拗ねるか」
「そういうことじゃ」
「ならば」
童虎を抱き締めたまま、ふっとシオンの気配が変わった、と思った次の瞬間。
墓地にいたはずの童虎は、シオンの私室にあるベッドの上に横たえられて、シオンにのしかかられていた。
「……っ!? お前、何をしたのじゃ?」
「知れたこと。瞬間移動だ」
「この聖域で何ということを……」
「私が教皇だ。文句を言う者はおるまい。十二宮をわざわざ上がるのが面倒なんでな。一度聖域の外へ飛んで、ここへ移動したまでのこと」
絶句する童虎の上で、シオンはしれっと言い返してきた。
「それとも、十二宮を一つずつ上がって、私に抱えられる様子を皆の前に晒されたかったのか?」
「冗談ではないわっ!」
売り言葉に買い言葉で思わず言い返した童虎は、まんまとシオンに言いくるめられたことを悟った。
「観念しろ、童虎。お前とて、十二宮を上がってくる時間がもどかしいと思ったのだろう?」
「それは……」
そう言われると、童虎は反論できない。
「素直になれ。黙って私に抱かれろ」
「……手荒なことをするでないぞ、このバカ羊」
「心得ている」
仕方なく白旗を揚げた童虎に、シオンは満足げに微笑した。
そっと頬に触れてきた手の温もりと思いがけず優しい仕草に、童虎はつい、覆い被さってくるシオンを見上げた。日頃の尊大な態度とは裏腹に、触れてくる手は童虎を気遣うようでもあり、戸惑っているようでもあった。
ゆっくりと近づいてくるシオンの整った顔に、つい見入ってしまいそうになる。童虎は目を閉じて、そっと重なってくるシオンの唇を受け入れた。
ただ軽く触れるだけのキスを何度か繰り返して、次第に深く重なってくるシオンの唇が、くすぐったいようでもどかしい。自分から動いてしまいそうになるのを踏みとどまって、童虎はシオンのするがままに任せた。
(不思議なものじゃな)
シオンとの付き合いは、もう250年近くになる。けれど、こんな風に触れ合うのはこれが初めてだというのが、何だか不思議だった。
童虎に体重をかけないようにと気遣いながら、それでも触れ合うシオンの胸で心臓が早鐘を打っているのが伝わってくる。昨夜童虎の寝込みを襲った時は性急に求めるように動いたシオンが、今は慎重に触れてくる。
そんなシオンが、どうしようもなく愛しくて切なかった。
(……じれったいのぉ)
じれた童虎は、シオンの首に腕を回して後頭部を抱え、ぐいと引き寄せて深く口づけて、自分からシオンの口腔に舌を潜り込ませた。
童虎が積極的に動いたのを驚いたように、シオンの動きが一瞬止まる。けれどすぐに立ち直って、童虎から主導権を奪う。
貪るように深く激しく口づけられて、シオンの吐息と唾液が絡む音に耳を犯されて、次第に理性が剥がれ落ちていく。
「シオン……」
呼びかけた自分の声が、自分のものではないような響きを帯びていた。シオンは一瞬驚いたような表情を見せたが、次の瞬間には立ち直って不敵な微笑を浮かべた。
「……随分と積極的だな、童虎」
「わしが欲しくて仕方ないくせに、お前がもたもたしておるからじゃ」
「短気なところは相変わらずだな」
見下ろしてくるシオンの目が、愛おしいものを見るように優しく細められる。そんな表情の一つ一つも、少しずつ熱くなってくる体も、愛おしいと童虎には思えた。
(いつの間に、こんなに惹かれておったのかの)
眠っている間に口づけられるまで、自分がどれほどシオンに惹かれているのか、童虎は全く気づいていなかった。シオンが自分に寄せていた想いにも。
再びシオンの唇が自分のそれを塞ぎ、口腔を舌で探られる感触に溺れそうになりながら、童虎は思った。
どうして今まで、そんな自分の心に気づかなかったのか、と。
「ん……っ」
余計なことは考えるなと言わんばかりに、口づけながらシオンの指が左耳の後ろの軟らかい部分をくすぐって、首筋へと下りていく。考えようとしたことは、形をなす前に霧散する。
木製の留め具を外し、服を脱がされて素肌を晒された。思いの外冷えた空気に触れて寒さを感じたのはけれどほんの一瞬で、すぐにシオンの熱を帯びた体に抱きすくめられ、熱い手のひらと唇と舌で愛撫された。
「ぁ……っ、ん……ぅっ」
胸から腹へと優しく撫で下ろされ、撫で上げられて、所々肌を吸われて刺激され、ついびくりと反応する。
体が熱くなってくることを、童虎は自覚した。
背中に感じるシーツの感触も、体の前面に感じるシオンの法衣の感触も、じわじわと童虎を追いつめてもどかしい。手触りのいい法衣の布地も、左右の合わせ目に施された刺繍や縫い込まれているビーズの感触すらも、今の童虎にはたまらない刺激だった。
「わし、だけ……っ」
法衣の胸倉を掴んで、童虎は喘ぎながら呟いた。
「どうした、童虎?」
問いかけてくるシオンの声にも、余裕がなくなってきている。
「お前も脱がぬかっ。服が擦れて……気持ち悪いのじゃ」
「ああ……それは気付かなかったな。すまない」
直接シオンの肌に触れたい。
けれどそれを口にするのは照れ臭くて、童虎はつい憎まれ口を叩いた。そんな童虎の心の内も、シオンには見透かされている。お互いに相手を欲しいと思う気持ちは同じだ、とシオンも気づいている。
童虎の中心で息づく熱に軽く触れて、シオンは童虎に深く口づけた。舌で口腔を探り舌を絡ませながら、シオンは器用に留め金を外して法衣を脱いで下着も取り去った。
重なってくる体に、シオンの熱に、浮かされそうになる。
「愛している、童虎」
そう告げた唇が、喉から胸へと滑り下りていく。
「わし、も……っ!」
応えなければ、と口を開くと同時に体の中心でそそり立つ熱に口づけられて、息が詰まった。
「あ……っ、ん――あっ、シオンッ!」
そのまま口腔深くに飲み込まれ、最も敏感な先端を舌で舐められて、童虎の体がびくびくと跳ねる。唇から漏れる嬌声が止まらない。
「あ……あぁっ!」
脊髄を駆け上がる強烈な刺激と、後ろに回されたシオンの指が体を開いていく感覚に、童虎は体を震わせた。
「シオン……シオンッ!」
童虎を傷つけないようにと気遣って蕾を解していくシオンの気持ちが嬉しくて、早く繋がりたいと逸る気持ちもわき上がってきて、行き場のない思いを童虎はシオンにぶつけた。
自分よりも遥かに体格のいいシオンの首にしがみついて、薄っすらと汗ばむシオンの首筋に噛みつくようなキスをした。
「童虎……欲しいのか?」
「……っ」
顔を上げて再び童虎を見下ろしてくるシオンに、童虎はただ頷いた。もともと大らかで素直で、子供のような面を持ち合わせていた童虎が見せる幼い仕草に、シオンは自然と微笑を浮かべた。
「挿れてもいいのか?」
「構わん――……っ」
じわじわと攻められて、中途半端な快感を味わわされるのが、戦闘で肉体にダメージを与えられるよりも辛い。
拗ねたような童虎の返事に、シオンは微笑しながら頷いて、童虎の腰を抱え上げた。蕾に猛った切先を宛がうと、童虎の意思に反して生理的に体が逃げようとする。それを押さえつけて、シオンはじわじわと童虎の中に侵入した。
「――っ!? ん……っ、う――……っ!」
女神の力で再び生を受け、肉体を経てから初めての交接が、童虎に苦痛を生む。顔を歪ませながらも、童虎は腕を伸ばしてシオンの太腿に触れ、シオンを促した。
「童虎……」
健気に求めてくる童虎が、ただ愛おしい。
シオンは童虎に軽く口づけて、ゆっくりと童虎を穿ち始めた。
「……ん、あ――……っ」
初めは苦痛を滲ませていた童虎の表情が、次第に陶酔した表情へと変わっていく。声音も、快楽を訴える艶のある声へと変わる。侵入したシオンを締め付けていた内襞も、少しずつほぐれて柔らかく絡みついてくるようになる。
「童虎――……っ」
「シオン……あっ、シオン――……っ!」
シオンも童虎も、お互いを呼び合って貪るように唇を吸った。
小柄な童虎はシオンの腕の中にすっぽりと抱きこまれてしまう。黄金聖闘士の中で最も小柄で、弟子の紫龍にさえ身長を抜かれてしまった所も愛らしくて、シオンは童虎の耳元に唇を寄せて囁きを注いだ。
「童虎――……」
シオンの首に腕を回してすがってくる童虎が、耳元で囁かれて軽く痙攣する。
「お前の中は、気持ちいいぞ」
「んっ……う、あ――……っ!」
ぐい、と奥を突かれて童虎の体が跳ねる。反動で中にいるシオンが締め上げられて、シオンも思わず呻いた。
「う……く………っ、童虎」
吐息を吐き出しながら呼びかけて、シオンは童虎の中心に手を伸ばして、屹立した器官を握って強くしごいた。
「あ――……っ、ダメ、じゃ……シオン、あぁっ!」
シオンの手の中で童虎の性器が大きく震えて、爆発した。同時に中にいるシオンも収縮した内襞に強く絞られて、シオンは童虎の中で果てた。
ふっと意識が浮上した童虎は、体にかかる重みに気づいた。
うっすらと目を開けると、自分に圧し掛かっている体が目に入った。しっかりと筋肉についた、鍛え上げられた体。自分とは質の違う素肌。髪にかかる吐息。
体に残るだるさには覚えがあって、童虎は記憶を辿る。
シオンに初めて抱かれて、その後も自分を求め続けるシオンに応えて二度、三度と体をつなげた。三度目に二人ほぼ同時に果てて、そのまま眠りこんでしまったのだと童虎は思い出した。そして今、情事の名残もそのままに、裸のままでシオンに抱きこまれた状態で眠っていたのだと気づく。
「……重い」
身じろぎをしてシオンの体をどかそうとするのだが、自分よりも遥かに体格がよくて体重も重いシオンはびくともしない。それでも何とかシオンの体の下から抜け出してベッドから降りようとしたのだが、寸前で再びシオンの腕に捕らえられた。
「どこへ行く?」
寝起きでかすれたシオンの声が問いかけてきて、童虎は目を丸くした。
「なんじゃ、起きておったのか」
「今、お前が私の腕から逃げようとしたのでな、目が覚めた」
「ならば早くどかぬか。重いのじゃ」
「このままお前が傍にいるのなら、どいてやろう」
「わしは体を洗いたいのじゃがの」
「私は別に構わぬが?」
童虎の上からは降りたものの、シオンはそのまま体を横たえて童虎に腕を絡ませてくる。抜け出そうと思っていたのだが、シオンの肌の温もりと感触が心地よくて、このままでもいいかと甘えてしまう。
ふと悪戯心が湧いて、童虎はシオンの広い胸板の上にえいっと乗り上げた。
「甘え足りぬか?」
「違うわっ。単なる仕返しじゃ」
童虎に乗られても全く堪えた様子のない、むしろあっさりと童虎の心の内を見抜いたシオンに、つい拗ねたように言い返してしまった。
「そうか」
照れ隠しだとバレているのだろう。シオンは微笑しながら余裕の表情を見せた。
243年も離れていたとはいえ、前の聖戦からずっと親友であり続け、二百年以上も教皇としてこの聖域に君臨し続けた男だ。ましてや、童虎を愛していると言って心ごと抱いてしまう男だ。これだけ密着した距離では、心を隠すことなどできない。
それでも、悪い気はしない。
(仕方がないの)
相手がシオンなのだから、と納得してしまう自分がいた。
「のぉ、シオン」
「何だ?」
シオンの胸の上から顔を見上げて呼びかけると、柔らかい視線が下りてきた。
「そういえば、まだ言うておらなんだの」
愛していると告げたシオンに応えようとしたものの、ことごとく愛撫で追い詰められて阻まれてしまったのだ。結局童虎の気持ちは、シオンに言えずにいた。
童虎は体を少し移動させて、シオンを真っ直ぐに見下ろした。
「わしも、お前を好いておるぞ」
口にするのは思っていた以上に恥ずかしくて、照れ隠しも手伝って童虎はそのままシオンに口づけた。唇を触れ合わせただけで離れようとした童虎だったが、シオンに後頭部をがっちり押さえられてままならなくなった。
「……んっ、ふ……」
口裂を舌で割られてシオンの侵入を許す。深く口腔を探られたと思ったら、世界が180度反転した。
「童虎……」
シオンの声が情欲に濡れる。一気に欲望が高まったのが、密着した体でわかった。
「お前、また……!?」
「私を煽ったのはお前だぞ、童虎」
観念しろ、と暗にシオンが訴えてくる。
「わしは、そういうつもりでは……ぁっ!」
首筋を吸われ、鋭敏な性器の先端を指の腹で擦られて、童虎はつい声を上げた。
それに気を良くしたシオンが本格的に童虎を攻めてくる。
「あ……っ、ん――……っ」
童虎は目を閉じて、シオンの愛撫を受け入れた。
Fin
written:2009.10.27
というワケで、久方ぶりのシオ童でありました。
今まで書いた作品とはちょっと違った方向から、二人の馴れ初めを書いてみました♪
ちょっとテンマ×童虎なテイストが入っているのは、当方の趣味です(汗)
できれば、童虎たんのお誕生日に間に合うようにアップしたかったのですが。。。
1週遅れになってしまいました(苦笑)