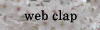Christmas Carol 1
幼い頃から、自分には何かが欠けていると思っていた。
両親から愛情を注がれ、何不自由なく育てられてきた。
習い事もしたし、スポーツクラブにも通った。
中学・高校時代は部活動にも熱中した。
友人も多かったし、バカ騒ぎをして叱られたこともあった。
けれど何かが足りない。
その足りない物が何なのか、どれほど考えても答えは出なかった。
同時に、不思議に思うことがあった。
幼い頃から、何度も同じ夢を見る。
誰かの死に目に遭う夢。
その人と離れることが哀しくて、身を引き裂かれるほどに悲しくて、泣き叫ぶ自分。
死ぬな、と何度も呼びかける自分。
名前を呼んでいるのはわかるけれど、その名前が思い出せない。
それだけではない。
生まれてから19年生きてきて、どこで学んだわけでもない、本を読んだわけでもないのに知っていることがある。
知らないはずのことを、口にすることがあった。
授業で有名な和歌を読んだ時、漢文の授業で出てきた例文。
何の知識もないはずなのに、スラスラ読んで内容を理解している自分がいた。
俺は、何なんだろう?
大学生になった今も、何度も自問自答する。
けれど相変わらず答えは出ないまま、何となく大学に進学して。
伊藤政樹は大学2年の冬を迎えていた。
---------------------------------------------------------------------
Kフィルハーモニー交響楽団のフルート奏者である片山幸太郎は、その日、大学時代の先輩にあたるファゴット奏者から一通のメールを受け取った。
「……第九演奏会の詳細について、か……」
メールを開いて中身を確認して、幸太郎はぽつりと呟いた。
クリスマスを目前に控えた2週間後の祝日に行われるコンサートの、エキストラ奏者への詳細な案内だった。
演目は、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱」
本場のヨーロッパでは演奏機会が少ない曲なのだが、日本では年末の風物詩として定着している。
その演奏会でオーケストラに本来所属しているフルート奏者が有給休暇を取るために、演奏者が足りなくなった……と幸太郎へ出演要請があったのが、10月の話。
特に予定もなく、自分が所属しているオーケストラとの練習日程も重なっていなかったため、幸太郎は出演を承諾した。
「仙台、か……」
その地名に、何か引っかかるものがあった。
最初に誘いを受けた時、行かなければならない、と幸太郎は思った。
特に思い当たる理由があるわけではない。
だが、行かなければならない、という焦りにも似た強烈な衝動が湧き上がってきた。
気がついた時には、手が勝手にキーを叩いて出演を承諾するメールを返信していた。
(……様が、待っておられる……)
宿泊するホテルや、練習会場にもなっているホールの場所、出演料などを確認しながら、幸太郎は頭のどこかで考えていた。
仙台行きが近づくにつれて、幸太郎は夢を見るようになった。
毎夜のように、同じ夢を見る。
死の床についている自分。
左半身が動かない自分。
その自分に向かって、何度も何度も「死ぬな!」と呼びかける人がいた。
「俺を置いて行くな!」
と……。
「お役に立てず、申し訳ございませんでした。先立つことをお許し下さい、……様」
呼びかける相手の名前は思い出せない。
相手に呼ばれる、自分の名も。
けれど、残った力を振り絞って、最期の力で右手を動かして、その人の手を握り返した。
「今まで御苦労だった、……。もし俺たちが生まれ変わることがあったら、その時は……その時は、また俺と共に来い。そして俺の背を守れ、いいな?」
「承知……致しました……、……様」
切れ切れになりながらそれだけ呟いて、目の前が真っ暗になったところで、目が覚める。
頬に残るのは涙の痕。
そして胸に残るのは、そのまま泣き叫びたくなるほどの深い悲しみと、切なさ。
自分に前世というものがあるのなら、恐らくこれはその時の記憶なのだろう、と幸太郎は思った。
相手とのやり取りから考えて、自分が仕えていた主との別れの場面なのだろう、と。
そして胸に残るこの感情から推測するに、自分はその主を愛していたのだ、誰よりも。
(まさか、仙台にいるのか?)
前世で死に別れた、その主が。
そしていよいよクリスマスが迫ってきた12月22日。
幸太郎は燕尾服や楽器など、必要な旅支度をして仙台へと向かった。
◆◇◆ ◆◇◆
新幹線で仙台に着いた幸太郎は、ホテルに荷物を預けて市内観光に出かけた。
リハーサル開始までは時間がある。
市内を見て回る余裕を持って、敢えて早い時間の新幹線に乗ったのだ。
杜の都、仙台。
仙台藩祖である伊達政宗によって開かれ、整備され、あちこちにその足跡が残る街だ。
(まずは、城にでも行ってみるか)
ホテルからタクシーで仙台城跡へ向かった幸太郎は、とりあえず城の手前にある資料展示館に立ち寄ることにした。
政宗の直筆書状や、実際に政宗が使っていた日用品などが展示されているのを見て回っている最中、幸太郎は奇妙な既視感に襲われた。
(知っている……)
その中のいくつかに、見覚えがあったのだ。
政宗が戦場で着用していた蒼い陣羽織。
政宗の愛刀、竜の爪とも六爪とも言われた、6本で一組になっている、政宗にしか扱えなかった景秀。
政宗がかぶっていた、弦月の前立てがついた兜。
加えて、幸太郎は何故か、展示されている書状をスラスラと読むことができた。書状の下に置かれている解説文に頼ることなく。
学校で習う以外に、書道をやった経験はない。筆で書かれた行書を読む知識など、幸太郎は持ち合わせていない。
にもかかわらず、だ。
そして伊達政宗の書状に書かれている花押。
目の前でそれをしたためていた人を、幸太郎は知っていた。
伊達政宗……
頭の中で、その名を呼ぶ。
とっさに、違う、と思った。
(その呼び方じゃない)
伊達政宗……政宗、さん……
(それも違う)
そして展示されている中の一つ。
政宗の腹心の部下であり、竜の右目との異名を取った片倉小十郎宛に送られた書状を見た瞬間。
「政宗様……」
幸太郎は、自然にそう呼んでいた。
(お前も花押書くの、上手くなったじゃねぇか、小十郎。俺も、頑張らねぇとな)
書状の字を目で追いながら、政宗の声が、口調が、脳裏に浮かんできた。
(死ぬな、小十郎! 俺を置いて行くんじゃねぇっ!)
同時に、悲痛な叫び声が脳内に響き渡った。
「政宗様……っ」
堰を切ったように、幸太郎の中に記憶が呼び覚まされてきた。
前世の自分。
自分と共に過ごしていた仲間たち。
そして誰よりも慕い、愛し、共に戦場を駆け、常にその背中を守り続けた主、伊達政宗。
「俺は……」
呆然と、呟いた。
「片倉小十郎、だったのか……」
◆◇◆ ◆◇◆
夕方からのリハーサルは、全く身が入らなかった。
前世が片倉小十郎だったと判明したとはいえ、今の小十郎は片山幸太郎として生きている。オーケストラのフルート奏者として、自分の仕事、責務は全うしなければならない。
気持ちを切り替えなければ……と思いつつも、蘇ってきた片倉小十郎の記憶に、小十郎としての自分に、気を取られていた。
もちろん、だからと言って気の抜けた演奏をしたわけではなかったのだが。
リハーサルを終え、顔見知りの演奏者と共に夕食を食べに出かけても、小十郎はどこか上の空だった。
(政宗様……)
自分は、死ぬ間際に約束したのだ。
もし自分たちが生まれ変わることがあったら、その時は。また政宗と共に生き、その背を守ると。
約束を違えるつもりはない。
生まれ変わった今でも、政宗は唯一無二の主であり、かけがえのない存在であり、命がけで守るべき相手だ。
戦乱の世が終わりを告げ、平和が訪れた現代であったとしても、なお。
(探さなければ、政宗様を)
どこにいるのかもわからない、同じ時代に生まれ合わせているという保証もない。
だが、自分が前世の記憶に導かれるように音楽の道へと進み、仙台へとやって来たように。
政宗もまた、無意識のうちに前世の記憶に導かれてこの地に来ているかもしれない、という確信があった。
小十郎はこの仙台の街を知らない。
政宗が仙台に入った頃、小十郎は脳卒中で倒れ、病の床に臥していた。利き手である左手が動かなくなり、剣を握ることも叶わなくなった。
政宗から預かっていた白石での療養を余儀なくされていた小十郎は、政宗がどのように仙台を発展させたのか、今になって初めて知ったのだ。
だが、政宗にとっては違う。
ここは政宗が作り上げた街だ。
生まれ育った米沢の地、青年期を過ごした岩出山の地と同様、あるいはそれ以上に愛着がある場所だ。
政宗は小十郎を見舞う度に、この仙台をどういった街にするのか、城をどうするのか、小十郎に知恵を貸すように求めつつ、頭の中で描いている計画を小十郎に話してくれた。
(ここに、おられるのか? 政宗様……)
思い出してしまった以上、何としても会わなければならない。
焦りにも似た気持ちが、小十郎の中に湧き上がっていた。
(政宗様……)
店を変えて飲みに行くという演奏家たちと別れ、色鮮やかな電飾に彩られた木々の下を一人歩きながら、小十郎は心の中で呼びかけ続けた。
「ハッピ・バースディ・トゥーユー!」
5分ほど、SENDAI光のページェントと銘打たれたイルミネーションの下を歩き続けた頃、小十郎の耳に十数人が騒ぐ声が聞こえてきた。
今日は祝日の前で、クリスマスも近く、忘年会シーズンでもある。
どこぞの大学生か、まだ年若い社会人が集団で騒いでいるのだろう、と小十郎はその横を通り過ぎようとした。
「ハッピ・バースディ ディア政樹ぃーーー!」
「ったく、やめろよ。1日早ぇんだよ」
その時、集団の中から聞こえてきた声に、小十郎は足を止めた。
聞き覚えのある声だった。
深みと独特の棘のようなものがある低い声。
印象的な、一度聞いたら忘れられないような声。
それは、懐かしい主の声だった。
「いいじゃねぇかよ、せっかく祝ってやってんだからよ」
「天皇誕生日と一緒って、なんか凄くね?」
「やっぱ持ってるよねー、マー君」
面白半分といった様子でからかわれている、集団の中心にいる青年を、小十郎は凝視した。
肩にかかるほどの、癖のある色素の薄い髪。
切れ長の目、すっきりしとした鼻梁、きりっと引きしまった口角。
眼力の鋭い、印象的な瞳。
記憶の中にある主の顔と、全く同じだった。
「その呼び方やめろって言ってんだろ。俺は……」
「政宗様……」
つい、呼びかけていた。
呼びかけられた青年は、小十郎を振り返って驚いたように見つめ返してきた。
見つめあったのは、ほんの刹那。
けれど、時間が止まったかのように、小十郎には感じられた。
見れば見るほど、似ている。
青年の鋭い眼光が、小十郎を射抜く。
そして感情を抑え込んだような低い声で、呼び返してきた。
「小十郎……」
青年は、伊達政宗その人だった。
きっかけは、政宗様の中の人がナレーションをやっている朝のワイドショーを見ていた時のことでした。
「ランキング探偵」と称して、全国のクリスマスイルミネーションを特集していた時に、出てきたのですよね、SENDAI光のページェントが。
それを見た瞬間。
この下で、現代の生まれ変わった双竜が再会するお話とか、ステキだなぁと思いまして。
書き始めたのはよいのですが……今の時点で、すでにクリスマスイブ。
日付ズレてんじゃねぇかっ!!(泣)
えー、前後編になるか、数章仕立てになるかわかりませんが、続きます(汗;)